光と影の寓話
このところ好きな映画を観る余裕がなかったので、妻子が実家に帰っている独身の春休み、吉祥寺のアップリンクで映画を楽しむ
20年前のハンガリー映画のリストア版、観終わってから以前に観ていたことを何となく思い出す
20世紀は電気の新しい時代、でも、アンシャン・レジームの名残もいたるところに、その混在が美しい。もちろん、前者が光で、後者が影
ここから余談へ
映画は、男性の飾りであった女性が自立すること、いわゆるフェミニズム運動も含まれていて、途中、男性の学者が「女性は感情的で下等であり、人の話を聞くことができない、云々」と、女性をこき下ろす演説が結構続くシーンがある。観ていた初老のご婦人二人が「この人の考え方ちょっと変わってるわね」と、思わず話し始めてしまう。それでスウィッチが入ったのか、彼女たちの会話は映画の最後まで断続的に続き、終映後、近くにいたおじさんに「映画館では喋ってはダメなんです、せっかくの映画が台無しだった」と説教されていた。
ウンウン、この映画の監督さんは女性で、あのシーンは今も変わらぬ男性への嫌味だったと思うんだけど、ストレートに初老のおばさんの心を打ちのめしてしまったことにちょっと驚き。この映画が、さらに公開から20年後に再上映された企画の意図にあるのかどうかわからないが、この閉塞感に満ちた今の時代に寛容さの必要性を訴えっていると思ったのに…。あのおじさんの態度は不寛容と断定していいのかと
映画館のなかで、色々と考えさせられた貴重な体験をした
やっぱり映画を映画館で観るのは楽しい
このところ好きな映画を観る余裕がなかったので、妻子が実家に帰っている独身の春休み、吉祥寺のアップリンクで映画を楽しむ
20年前のハンガリー映画のリストア版、観終わってから以前に観ていたことを何となく思い出す
20世紀は電気の新しい時代、でも、アンシャン・レジームの名残もいたるところに、その混在が美しい。もちろん、前者が光で、後者が影
ここから余談へ
映画は、男性の飾りであった女性が自立すること、いわゆるフェミニズム運動も含まれていて、途中、男性の学者が「女性は感情的で下等であり、人の話を聞くことができない、云々」と、女性をこき下ろす演説が結構続くシーンがある。観ていた初老のご婦人二人が「この人の考え方ちょっと変わってるわね」と、思わず話し始めてしまう。それでスウィッチが入ったのか、彼女たちの会話は映画の最後まで断続的に続き、終映後、近くにいたおじさんに「映画館では喋ってはダメなんです、せっかくの映画が台無しだった」と説教されていた。
ウンウン、この映画の監督さんは女性で、あのシーンは今も変わらぬ男性への嫌味だったと思うんだけど、ストレートに初老のおばさんの心を打ちのめしてしまったことにちょっと驚き。この映画が、さらに公開から20年後に再上映された企画の意図にあるのかどうかわからないが、この閉塞感に満ちた今の時代に寛容さの必要性を訴えっていると思ったのに…。あのおじさんの態度は不寛容と断定していいのかと
映画館のなかで、色々と考えさせられた貴重な体験をした
やっぱり映画を映画館で観るのは楽しい
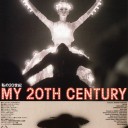

コメント
“時代の寛容”の範疇には入らないおふたりかな。
おじさんも、上映中にひとこと言ってくれればよかったのにね、、、と思いますけど、言わないで聞こえてくるイライラと、言ってしまって残り時間気づまりなのと、葛藤あったかも~(笑) その悶々は日本人的ですかね。ニッコリ笑って「しー! …サンキュ!」ってやれない不器用さありますよね。
やってみたいけど、日本人的で、不器用な私には無理だ〜(笑
「流」、牯嶺街少年殺人事件のような美しさは期待しないでくださいね
雰囲気としては香港アクション映画に近いような