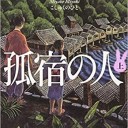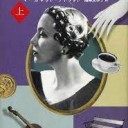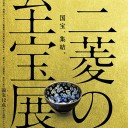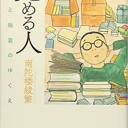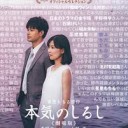あれよあれよという間に、この日記を書くのに残された期間は10日ほどに
書き残したことというか、感想を書きたかった映画、小説は山ほどあって、そのなかあえて一つと言えばこれかな
カズオ・イシグロのノーベル賞受賞後初となる小説「クララとお日さま」
人工知能のお話。人工知能は人になれるか?、言い換えれば人工知能と人はどちらが優秀か?なんて問いへの答えは、ひと昔前に決着のついており、今更なんだけど
そんな王道のテーマを使って、古臭くなく、新鮮なお話を紡ぐカズオ・イシグロの才能に改めて感動。伊達にノーベル賞を取っているわけでなく、ノーベル賞を取ってなくて凄い作家はごまんといるけど、ノーベル賞を取った作家はやはり凄いことに納得
答えがないのに、読後感の爽快感に素直に感動
いやいや、答えがないから爽快なんだと納得
書き残したことというか、感想を書きたかった映画、小説は山ほどあって、そのなかあえて一つと言えばこれかな
カズオ・イシグロのノーベル賞受賞後初となる小説「クララとお日さま」
人工知能のお話。人工知能は人になれるか?、言い換えれば人工知能と人はどちらが優秀か?なんて問いへの答えは、ひと昔前に決着のついており、今更なんだけど
そんな王道のテーマを使って、古臭くなく、新鮮なお話を紡ぐカズオ・イシグロの才能に改めて感動。伊達にノーベル賞を取っているわけでなく、ノーベル賞を取ってなくて凄い作家はごまんといるけど、ノーベル賞を取った作家はやはり凄いことに納得
答えがないのに、読後感の爽快感に素直に感動
いやいや、答えがないから爽快なんだと納得
久しぶりに来てみたら、日記が書けなくなるお知らせがあって、少しびっくり
始まりがあれば、終わりあり、しょうがないか
次をどうするかはすぐには思い浮かばないけど、このまま日記生活は終わるのかなとも、わからないけどね
急に春が来て、通勤時、どの道を通って駅に行くか悩ましい
あの道のコブシも気になるし
あのお宅の山椒の立派な株も気になるし
あの花壇の球根も気になる
始まりがあれば、終わりあり、しょうがないか
次をどうするかはすぐには思い浮かばないけど、このまま日記生活は終わるのかなとも、わからないけどね
急に春が来て、通勤時、どの道を通って駅に行くか悩ましい
あの道のコブシも気になるし
あのお宅の山椒の立派な株も気になるし
あの花壇の球根も気になる
ルール?展@21_21 DESIGN SIGHT
2021年11月26日 日常
ネット上のレビューを読んで、興味をもった展覧会
意外にも人気があるらしく、週末の予約はほぼ満杯で、テレワークと言って職場を抜け出して、平日に訪れる
会場に入って驚いたのは、お客さんの若さ、ほぼ学生!?普段私が行く印象派や仏教芸術のメジャーな展覧会は年配の人が多いのに…
だいたいの内容はいくつかのレビューを読んで知っており、ルールについての私たちの常識を覆してくれて、目からウロコの体験ができるものと期待していた
いやいや、作品はユニークなんだけど、こねくり回されてて、ついてゆくのに四苦八苦
さらに、ルールの展覧会だけあって、そんじゅそこらにルールが小さい字で書いてあるのだが、おじさんたちは老眼で小さい文字を読むのが大変
さらに、目玉である参加型の作品で、次々と出される二択の質問に制限時間内に答えを決めて、プロジェクターで足元に映し出された回答エリアへ移動しなければならない。スマホゲームで鍛えられてる若いものとは違い、年々運動神経が衰えてゆく年寄には慌ただしく、楽しめない
ルールの歴史と意味のようなものは、きっと言葉で説明した方が伝わりやすいと思うのだが、あえてそこを同じ空間で身体性を通して体験してもらい、ルールのダイナミックさ感じてもらおうという意図は伝わったが、
有料の展覧会会場で、それをやることが難しいこともよくわかった
消化不良というか、満足しきれない展覧会
ただ、若い人たちには、フォトジェニックな空間ということで受けていたのか、マスク越しに見える顔は楽しそうに見えた
ルールって面白いねではなく、若いって良いね!ということがよくわかった展覧会
意外にも人気があるらしく、週末の予約はほぼ満杯で、テレワークと言って職場を抜け出して、平日に訪れる
会場に入って驚いたのは、お客さんの若さ、ほぼ学生!?普段私が行く印象派や仏教芸術のメジャーな展覧会は年配の人が多いのに…
だいたいの内容はいくつかのレビューを読んで知っており、ルールについての私たちの常識を覆してくれて、目からウロコの体験ができるものと期待していた
いやいや、作品はユニークなんだけど、こねくり回されてて、ついてゆくのに四苦八苦
さらに、ルールの展覧会だけあって、そんじゅそこらにルールが小さい字で書いてあるのだが、おじさんたちは老眼で小さい文字を読むのが大変
さらに、目玉である参加型の作品で、次々と出される二択の質問に制限時間内に答えを決めて、プロジェクターで足元に映し出された回答エリアへ移動しなければならない。スマホゲームで鍛えられてる若いものとは違い、年々運動神経が衰えてゆく年寄には慌ただしく、楽しめない
ルールの歴史と意味のようなものは、きっと言葉で説明した方が伝わりやすいと思うのだが、あえてそこを同じ空間で身体性を通して体験してもらい、ルールのダイナミックさ感じてもらおうという意図は伝わったが、
有料の展覧会会場で、それをやることが難しいこともよくわかった
消化不良というか、満足しきれない展覧会
ただ、若い人たちには、フォトジェニックな空間ということで受けていたのか、マスク越しに見える顔は楽しそうに見えた
ルールって面白いねではなく、若いって良いね!ということがよくわかった展覧会
久々の宮部みゆき、でも宮部みゆきの江戸ものは初めて?
この前に読んだアトウッド女史の作品が曲者だっただけに、まずは、その読みやすさに感動
身分性が厳しかった近世の話、今とは全然違う世界へ違和感なく入っていけたのは、やっぱり宮部みゆきの語りのうまさだと思う
登場人物たちが、身分制を含めた様々な不条理に楯突こうとしながらも、当然身分が上の者は怖いと臆病者になってしまう
臆病者はいつまでも臆病者で、人はそんなに変われないと思うけど、小説なので登場人物たちは見事に成長して変わってゆく
そんな都合の良い話があるのかというツッコミも忘れて、話の先が知りたくて読み進む
あっという間に、あっさり読了
あ〜、楽しかった、満足
ただ不思議なんだけど、読み終わったあとの余韻は、苦労して読んだアトウッド作品の方が長い
この前に読んだアトウッド女史の作品が曲者だっただけに、まずは、その読みやすさに感動
身分性が厳しかった近世の話、今とは全然違う世界へ違和感なく入っていけたのは、やっぱり宮部みゆきの語りのうまさだと思う
登場人物たちが、身分制を含めた様々な不条理に楯突こうとしながらも、当然身分が上の者は怖いと臆病者になってしまう
臆病者はいつまでも臆病者で、人はそんなに変われないと思うけど、小説なので登場人物たちは見事に成長して変わってゆく
そんな都合の良い話があるのかというツッコミも忘れて、話の先が知りたくて読み進む
あっという間に、あっさり読了
あ〜、楽しかった、満足
ただ不思議なんだけど、読み終わったあとの余韻は、苦労して読んだアトウッド作品の方が長い
カナダを代表する作家で、ノーベル文学賞の候補にも挙がっているらしい
20世紀の近現代の波に揉まれる女性のお話
近現代の波に揉まれる女性と書けば、なんとなくNHKの朝の連ドラを連想するがそんなに甘くない。朝の連ドラと違って出てくるのはみんな性格悪し。逆に言えば、自分に素直だとも
文体、構成ともにかなり癖のある小説で、読むのに骨が折れる。読了後、訳者の解説を読んで、その癖に納得
内容とは関係ないが、
ボタンって漢字で書くと釦なのね、この漢字に馴染みがなく、「釦工場」が読めなかった
題名の「昏き眼」って盲目のことなのね、言われてみれば、確かにそうだ
20世紀の近現代の波に揉まれる女性のお話
近現代の波に揉まれる女性と書けば、なんとなくNHKの朝の連ドラを連想するがそんなに甘くない。朝の連ドラと違って出てくるのはみんな性格悪し。逆に言えば、自分に素直だとも
文体、構成ともにかなり癖のある小説で、読むのに骨が折れる。読了後、訳者の解説を読んで、その癖に納得
内容とは関係ないが、
ボタンって漢字で書くと釦なのね、この漢字に馴染みがなく、「釦工場」が読めなかった
題名の「昏き眼」って盲目のことなのね、言われてみれば、確かにそうだ
ここの誰かの日記で知ったような気もするけど、よく思い出せない、教えてくれた人ごめんなさい
ちょっとホードボイルド風の語り口が読みやすくて、スイスイ進む
犯人の手記と捜査のお話がパラレルに進む
読み残しのページがかなり薄くなっても、犯人の影も形も見えてこない。犯人がわからないまま終わってしまうのではと心配になる
ほんと、最後の最後で、急に謎解きが展開して、あ〜なるほどねと納得
やっと私のなかで、北欧ミステリーブーム到来か
有名どころをぼちぼちと齧っていく予定
ちょっとホードボイルド風の語り口が読みやすくて、スイスイ進む
犯人の手記と捜査のお話がパラレルに進む
読み残しのページがかなり薄くなっても、犯人の影も形も見えてこない。犯人がわからないまま終わってしまうのではと心配になる
ほんと、最後の最後で、急に謎解きが展開して、あ〜なるほどねと納得
やっと私のなかで、北欧ミステリーブーム到来か
有名どころをぼちぼちと齧っていく予定
書き逃した映画の感想
西川ワールドにはクセのある男性主人公がつきもので、見ているものを彼女の作った世界へ導いてくれる
蛇イチゴの宮迫、ディア・ドクターの鶴瓶、そして永い言い訳のもっくん、
みんな、浮世との関わりで、最初は歯車が少し食い違っただけなのに、ズレはだんだん大きくなって、最後には首が回らなくなる
今回の役所広司も首が回らなくなる
人を殺して、懲役喰らった務所帰りの男の再生のお話
カンヌを取った役所主演の映画「ウナギ」と設定が似ている
そう言えばウナギの監督は、今回の作品の原作者佐木隆三の作品「復讐するは我にあり」を映画化しており、繋がりを感じる
「復讐…」はろくでもない、近代的暴力に満ちた世界を描いているが
この「すばらしき世界」では、ポストモダンの福祉と寛容に満ちた素晴らしい世界が描かれている。果たして主人公は再生できるのか、それは見てのお楽しみ
もちろん、世の中素晴らしいことばかりでなく、暴力は「いじめ」という形で陰湿に残っており、大量消費とタグを組むマスコミの建前ばかりの正義感もあてにならない
西川ワールドにはクセのある男性主人公がつきもので、見ているものを彼女の作った世界へ導いてくれる
蛇イチゴの宮迫、ディア・ドクターの鶴瓶、そして永い言い訳のもっくん、
みんな、浮世との関わりで、最初は歯車が少し食い違っただけなのに、ズレはだんだん大きくなって、最後には首が回らなくなる
今回の役所広司も首が回らなくなる
人を殺して、懲役喰らった務所帰りの男の再生のお話
カンヌを取った役所主演の映画「ウナギ」と設定が似ている
そう言えばウナギの監督は、今回の作品の原作者佐木隆三の作品「復讐するは我にあり」を映画化しており、繋がりを感じる
「復讐…」はろくでもない、近代的暴力に満ちた世界を描いているが
この「すばらしき世界」では、ポストモダンの福祉と寛容に満ちた素晴らしい世界が描かれている。果たして主人公は再生できるのか、それは見てのお楽しみ
もちろん、世の中素晴らしいことばかりでなく、暴力は「いじめ」という形で陰湿に残っており、大量消費とタグを組むマスコミの建前ばかりの正義感もあてにならない
どんと背中を押されて、水曜日に食べに行ってきました
田無のさらしな
テレワークで、かつ午後イチのオンライン会議が入ってなくて、さらに天気が良くてという三条件が揃ったら、行くしかないでしょと
武蔵境通りをビュンビュン、自転車を飛ばしたら、あっという間に田無駅
空腹は最大のエネルギー
駅近の路地にひっそり佇む蕎麦屋さん、中野店は一度行ったことがあるけど、こちらは初めて
緊急事態宣言下の平日の昼過ぎ、お客さんはまばら
初めてのお店のお品書き、美味しいものを見逃さまいと、端から端まで三往復もしたのに、決めたのはお品書きには載っていない、玄関にサンプルが置いてあった昼定食のそば御前、定食についていた栗おこわについ惹かれて。
そばは菊切りのせいろ、うん季節だね
そしてもちろん無花果の味噌焼きも注文
定食の小鉢は選べて、揚げ出し豆腐に。揚げ物は温かいうちにいただこうと、蕎麦をいただく前に口をつけたら、いわゆる豆で作った豆腐ではなく、ごま豆腐のような澱粉粉で固めたつるりとした食感のものを揚げたもので、うまいと驚く!そういえば、店員さんが蕎麦豆腐…と言ってような。もうおじんで、言われたことが聞き取れてないことが多くて、こういう新鮮な体験が最近多いような(汗、汗
蕎麦を食べ終わった頃に無花果登場
あ、この食感ね、ネットリではなく、さっぱりとした無花果に、くるみと蕎麦の入ってる?お味噌、甘塩っぱくて美味しい!
定食についていた天ぷらが意外とさっぱりとしてて、まだまだいけるので、デザートの3点盛りを追加で注文
蕎麦のカステラ、蕎麦のおはぎ、抹茶羊羹
蕎麦はもちろん、サイドメニューが楽しいお店、満足!
美藤さん、ありがとう
今年やり残したことは、おすすめの例の緑地へ行くこと
田無のさらしな
テレワークで、かつ午後イチのオンライン会議が入ってなくて、さらに天気が良くてという三条件が揃ったら、行くしかないでしょと
武蔵境通りをビュンビュン、自転車を飛ばしたら、あっという間に田無駅
空腹は最大のエネルギー
駅近の路地にひっそり佇む蕎麦屋さん、中野店は一度行ったことがあるけど、こちらは初めて
緊急事態宣言下の平日の昼過ぎ、お客さんはまばら
初めてのお店のお品書き、美味しいものを見逃さまいと、端から端まで三往復もしたのに、決めたのはお品書きには載っていない、玄関にサンプルが置いてあった昼定食のそば御前、定食についていた栗おこわについ惹かれて。
そばは菊切りのせいろ、うん季節だね
そしてもちろん無花果の味噌焼きも注文
定食の小鉢は選べて、揚げ出し豆腐に。揚げ物は温かいうちにいただこうと、蕎麦をいただく前に口をつけたら、いわゆる豆で作った豆腐ではなく、ごま豆腐のような澱粉粉で固めたつるりとした食感のものを揚げたもので、うまいと驚く!そういえば、店員さんが蕎麦豆腐…と言ってような。もうおじんで、言われたことが聞き取れてないことが多くて、こういう新鮮な体験が最近多いような(汗、汗
蕎麦を食べ終わった頃に無花果登場
あ、この食感ね、ネットリではなく、さっぱりとした無花果に、くるみと蕎麦の入ってる?お味噌、甘塩っぱくて美味しい!
定食についていた天ぷらが意外とさっぱりとしてて、まだまだいけるので、デザートの3点盛りを追加で注文
蕎麦のカステラ、蕎麦のおはぎ、抹茶羊羹
蕎麦はもちろん、サイドメニューが楽しいお店、満足!
美藤さん、ありがとう
今年やり残したことは、おすすめの例の緑地へ行くこと
三菱の至宝展@三菱一号館美術館
2021年9月25日 日常
9月のあたま、久しぶりに出社した機会に、曜変天目に会いに大手町へ
静嘉堂文庫と東洋文庫の収蔵品の中から、岩崎家が集めた至宝を見せてくれる
いやいや見応えあります、この国の美意識の歴史を知るのに重要な書と絵画そして器が並ぶ
これが教科書に載っていたあれですかと感心しながら、眺める
この展覧会、これらの品々を集めた岩崎家の歴代当主の鑑賞眼も絡めての展示が面白く
私は漢籍も読めないし、くずし字も読めない、中国や朝鮮半島の官窯の名前も知らない、けどなんとなく、わかったような気になる
ちなみに私が長年紅茶を入れて愛用しているサーモスの水筒の内側、上半分には茶渋がつき、下半分は塗装が禿げて下地の金属光沢が見え、なかなかの成長ぶりである。この水筒の内側をのぞいていると、曜変天目じゃないけど宇宙を見ているような気分を感じさせる
何かが反応して、そこから波動のようなものが出て、伝わり、私の中でさらに何かが変わる
静嘉堂文庫と東洋文庫の収蔵品の中から、岩崎家が集めた至宝を見せてくれる
いやいや見応えあります、この国の美意識の歴史を知るのに重要な書と絵画そして器が並ぶ
これが教科書に載っていたあれですかと感心しながら、眺める
この展覧会、これらの品々を集めた岩崎家の歴代当主の鑑賞眼も絡めての展示が面白く
私は漢籍も読めないし、くずし字も読めない、中国や朝鮮半島の官窯の名前も知らない、けどなんとなく、わかったような気になる
ちなみに私が長年紅茶を入れて愛用しているサーモスの水筒の内側、上半分には茶渋がつき、下半分は塗装が禿げて下地の金属光沢が見え、なかなかの成長ぶりである。この水筒の内側をのぞいていると、曜変天目じゃないけど宇宙を見ているような気分を感じさせる
何かが反応して、そこから波動のようなものが出て、伝わり、私の中でさらに何かが変わる
1984年に生まれて
2021年9月24日 日常
著者の郝景芳は1984年天津生まれで、大学で物理や経済を勉強しながら、小説を書いていたらしい。この小説は大学院終了後に書いた二つ目の長編小説、
ジョージ・オーウェルの1984、唐詩、SFっぽい仕掛け、いろいろあって楽しめます
世界は回転するスピードをどんどんとあげ、そこでは新しい自由な、言い換えれば行き過ぎた資本主義の空間と価値観が生み出されては、消費されることが繰り返される。というのに、主人公の愚鈍な私は、取り残され、もがき苦しみ、何も生まれない回想に明け暮れる
凡人が悩むのはどこの国も同じ
解決策は二つ
ひとつは世界が動いているなら、自分もノマドとなり動き続ければ良い。風になれ!
そしてもうひとつの解決は、自己を肯定するには歴史を肯定する。パラパラと流動する世界についていけないなら、もっと巨視的、もっと長いスパンで世界を見据えて、くるりんぱっと着地する。大地に根付け!
さて、主人公の選択は!?
ジョージ・オーウェルの1984、唐詩、SFっぽい仕掛け、いろいろあって楽しめます
世界は回転するスピードをどんどんとあげ、そこでは新しい自由な、言い換えれば行き過ぎた資本主義の空間と価値観が生み出されては、消費されることが繰り返される。というのに、主人公の愚鈍な私は、取り残され、もがき苦しみ、何も生まれない回想に明け暮れる
凡人が悩むのはどこの国も同じ
解決策は二つ
ひとつは世界が動いているなら、自分もノマドとなり動き続ければ良い。風になれ!
そしてもうひとつの解決は、自己を肯定するには歴史を肯定する。パラパラと流動する世界についていけないなら、もっと巨視的、もっと長いスパンで世界を見据えて、くるりんぱっと着地する。大地に根付け!
さて、主人公の選択は!?
ドライブ・マイ・カー
2021年9月20日 日常 コメント (2)
これもテレワークの合間に抜け出して、見た映画
カンヌで賞を取ったことが日本で話題になった「ドライブ・マイ・カー」
監督は、劇場で上映される映画を空気を読まずに6時間に編集したことで有名なあの濱口竜介(世の中ではあまり有名でないかも!?)
彼が脚本を担当した「スパイの妻」、楽しい映画ではなかったが、心動かされた
「ドライブ・マイ・カー」では脚本と監督を担当、期待しないわけがない
まず、タイトルが出てくるまでの前振りの長いこと、映画自体が3時間だと聞いていたこともあり、タイトル前が延々と続いて、今回も普通の映画とは違うと構えてしまう(笑
話はシンプルで、映画が始まってしまえば、どんどん時間が過ぎてゆき、あっという間の3時間。なんだ構える必要なんてないじゃんと。監督も大人になったのかな?
映画は、今は亡き人に裏切られ、この世に残されてしまった二人の男女の出会いと彼らの再生の物語
男は元俳優の舞台監督、女はドライバー、でも男女の関係は一切なし
男が監督をする劇中劇の舞台オーディションと練習風景が、男女二人の会話とパラレルに展開する、このあたり安心して見れます。オーディションと練習風景に適度な緊張感があって、飽きない
終わり近くで、北へ向かうロードムービに展開し、ニンマリ。詳しくは見てのお楽しみ
現代の映像作品についての熱い思いも伝わってくる
映像があって、音声があって、作品はリアルをリアルに見せてくれるけど、
デジタル技術がどんなに進歩しても、映像だけでは表すことができない、悲しみや喜びのような単語でも表すことのできない何かがあって。それを伝える技法を劇中作の現代演劇も交えながら示してくれる
この何かを伝えるためには3時間必要なのねと納得
ちなみに、西島秀俊演じる主人公の乗っている車は名車SAAB 900
映画を俯瞰するポジションから、少し生意気な役を演じる岡田将生の乗る車が、同じスウェーデン車で、おしゃれで安全安心のVolvo V40(おそらく、間違ってたらごめんなさい)
このチョイスも絶妙で納得
カンヌで賞を取ったことが日本で話題になった「ドライブ・マイ・カー」
監督は、劇場で上映される映画を空気を読まずに6時間に編集したことで有名なあの濱口竜介(世の中ではあまり有名でないかも!?)
彼が脚本を担当した「スパイの妻」、楽しい映画ではなかったが、心動かされた
「ドライブ・マイ・カー」では脚本と監督を担当、期待しないわけがない
まず、タイトルが出てくるまでの前振りの長いこと、映画自体が3時間だと聞いていたこともあり、タイトル前が延々と続いて、今回も普通の映画とは違うと構えてしまう(笑
話はシンプルで、映画が始まってしまえば、どんどん時間が過ぎてゆき、あっという間の3時間。なんだ構える必要なんてないじゃんと。監督も大人になったのかな?
映画は、今は亡き人に裏切られ、この世に残されてしまった二人の男女の出会いと彼らの再生の物語
男は元俳優の舞台監督、女はドライバー、でも男女の関係は一切なし
男が監督をする劇中劇の舞台オーディションと練習風景が、男女二人の会話とパラレルに展開する、このあたり安心して見れます。オーディションと練習風景に適度な緊張感があって、飽きない
終わり近くで、北へ向かうロードムービに展開し、ニンマリ。詳しくは見てのお楽しみ
現代の映像作品についての熱い思いも伝わってくる
映像があって、音声があって、作品はリアルをリアルに見せてくれるけど、
デジタル技術がどんなに進歩しても、映像だけでは表すことができない、悲しみや喜びのような単語でも表すことのできない何かがあって。それを伝える技法を劇中作の現代演劇も交えながら示してくれる
この何かを伝えるためには3時間必要なのねと納得
ちなみに、西島秀俊演じる主人公の乗っている車は名車SAAB 900
映画を俯瞰するポジションから、少し生意気な役を演じる岡田将生の乗る車が、同じスウェーデン車で、おしゃれで安全安心のVolvo V40(おそらく、間違ってたらごめんなさい)
このチョイスも絶妙で納得
その日、カレーライスができるまで@吉祥寺
2021年9月18日 日常
テレワークになり時間の使い方がとても自由に
オンラインの打ち合わせが夕方だったので、金曜日の昼間、吉祥寺で映画を見る。昼の回なのに満席、席ひとつ飛ばしで定員半分だけどね
映画は、リリー・フランキーの一人芝居、「その日、カレーライスができるまで」
一人芝居は、登場人物が一人なので、どうしても無理が出てくるというか、一人では話が進み切らない。そこの無理を通すために、リアルでない不自然な演出に頼らざるを得ない。この作品では、ラジオの奇跡的なタイミングや、ここぞという時に倒れてくれる写真スタンドなど、他にもいろいろ、小道具満載です。
しかし、リアルが良いというわけではなく、観ているものがストーリーに入り込めれば、リアルじゃなくても良しだと思う。
ということで、リアルではない、ちょっと昭和の雰囲気のするストレートなドラマを50分楽しむ
リリー・フランキーの作るカレーは、令和の厨房男子が作るようなスパイスが何種類も入っているおしゃれなカレーではなく、市販のルーを使って3日煮込んだ昭和のカレー。カレーを仕込むところから始まり、盛り付けられたカレーで終わる
ラスト、ウキウキした気分を、流行りのサックスブルーのバンドカラーシャツに込めたあたりも、素直過ぎやしないかと突っ込みたくなるが、これも演出かと
大好きなリリー・フランキーなので全部許す!
オンラインの打ち合わせが夕方だったので、金曜日の昼間、吉祥寺で映画を見る。昼の回なのに満席、席ひとつ飛ばしで定員半分だけどね
映画は、リリー・フランキーの一人芝居、「その日、カレーライスができるまで」
一人芝居は、登場人物が一人なので、どうしても無理が出てくるというか、一人では話が進み切らない。そこの無理を通すために、リアルでない不自然な演出に頼らざるを得ない。この作品では、ラジオの奇跡的なタイミングや、ここぞという時に倒れてくれる写真スタンドなど、他にもいろいろ、小道具満載です。
しかし、リアルが良いというわけではなく、観ているものがストーリーに入り込めれば、リアルじゃなくても良しだと思う。
ということで、リアルではない、ちょっと昭和の雰囲気のするストレートなドラマを50分楽しむ
リリー・フランキーの作るカレーは、令和の厨房男子が作るようなスパイスが何種類も入っているおしゃれなカレーではなく、市販のルーを使って3日煮込んだ昭和のカレー。カレーを仕込むところから始まり、盛り付けられたカレーで終わる
ラスト、ウキウキした気分を、流行りのサックスブルーのバンドカラーシャツに込めたあたりも、素直過ぎやしないかと突っ込みたくなるが、これも演出かと
大好きなリリー・フランキーなので全部許す!
去年に続いて二度目の話なので、今回はそんなに驚かなかった、
とは言え、やはり驚いた!
何か弱みを握られてて、辞めないとバラすぞと脅されたのかと穿ってしまうほどの、急な方向転換
政治の世界はわからないね
とは言え、やはり驚いた!
何か弱みを握られてて、辞めないとバラすぞと脅されたのかと穿ってしまうほどの、急な方向転換
政治の世界はわからないね
ファイザー製ワクチン
2021年8月5日 日常コロナワクチンの接種、高齢者でも、医療従事者でもなく、基礎疾患のない私にはお鉢はまだまだ回ってこないだろうなと思っていたら
年寄りにあまり人気がないのか、五十路の私のところまで、順番が回ってきた
市の集団接種の予約を取って、1回目を打ってくる、種類はファイザー
入場してから出てくるまで、20分ぐらい、早い!簡単!副作用なし!
これが7月始めのお話し
2回目の接種、こちらは先週末のお話し
念のため、二日休みが取れるようにと、2回目は週末の金曜日
2回目も接種会場は空いており、入場から終わるまで20分、読もうと思って持っていった文庫本、5ページも進まないうちに建物の外へ
打った日の夜から熱が出始め、翌日に37.9のピーク
なかなか辛いけど、イブプロフェンを飲んで寝てれば、我慢できないこともないが、なんせ眠い
夏休みだと思って、週末の二日間はダラダラと過ごす
たるいので横になって文庫本の続きを読むけど、いつの間にか寝入って、寝汗で目覚める
打った方の腕の脇の下のリンパ節が痛い、普段意識できないリンパ節ってこれなんだと軽く感動
だるさはなんとなく、月曜まで続くも、許せるレベルに
国内でも、国際的にも、私なんてワクチン優先度からしたらもっと後ろであるはずなのに、死んだ目の総理の人気取りのための接種事業に乗っかって、ワクチンを打ってもらうのは本意ではないが、対面の仕事をするときの気遣いが少し減って、気が楽と目論んでた
でも、今回のウィルス、ワクチン打っててもウィルスのキャリアーにはなるらしく、僕打ってますからといって、即以前の生活に戻れるわけではない
まだまだマスクとテレワーク生活は続くということね
年寄りにあまり人気がないのか、五十路の私のところまで、順番が回ってきた
市の集団接種の予約を取って、1回目を打ってくる、種類はファイザー
入場してから出てくるまで、20分ぐらい、早い!簡単!副作用なし!
これが7月始めのお話し
2回目の接種、こちらは先週末のお話し
念のため、二日休みが取れるようにと、2回目は週末の金曜日
2回目も接種会場は空いており、入場から終わるまで20分、読もうと思って持っていった文庫本、5ページも進まないうちに建物の外へ
打った日の夜から熱が出始め、翌日に37.9のピーク
なかなか辛いけど、イブプロフェンを飲んで寝てれば、我慢できないこともないが、なんせ眠い
夏休みだと思って、週末の二日間はダラダラと過ごす
たるいので横になって文庫本の続きを読むけど、いつの間にか寝入って、寝汗で目覚める
打った方の腕の脇の下のリンパ節が痛い、普段意識できないリンパ節ってこれなんだと軽く感動
だるさはなんとなく、月曜まで続くも、許せるレベルに
国内でも、国際的にも、私なんてワクチン優先度からしたらもっと後ろであるはずなのに、死んだ目の総理の人気取りのための接種事業に乗っかって、ワクチンを打ってもらうのは本意ではないが、対面の仕事をするときの気遣いが少し減って、気が楽と目論んでた
でも、今回のウィルス、ワクチン打っててもウィルスのキャリアーにはなるらしく、僕打ってますからといって、即以前の生活に戻れるわけではない
まだまだマスクとテレワーク生活は続くということね
イサム・ノグチ展@上野
2021年7月18日 日常 コメント (2)
上野の都立で、イサム・ノグチに会ってきた
本当は、美藤さんのように、高松の庭園美術館へ行きたいところだが、四国へ行くあてもなく
上野で見られるなら、それは便利かと思い、梅雨明けの空がキレイな上野へ
現代ものの彫刻は鑑賞が難しい、形は抽象化され、色彩に乏しい
どう向き合ったらいいのか戸惑う
「あかり」シリーズという和紙と針金でできた暖かく親しみのある照明を配置した心地良い空間を作り、そこに作品を並べることで、難解な彫刻への取っ付き難さはかなり抑えられている
そう、今回の展覧会の売りは、イサム・ノグチ空間を楽しむこと
圧巻は、最後の高松牟礼町の美術館を再現した、「牟礼の石彫」の部屋
コロナの人数制限のおかげで、ゆっくりとイサム・ノグチ空間に浸れて、幸せ
あ〜、やっぱり、高松の吹きっさらしの庭で観たい!
本当は、美藤さんのように、高松の庭園美術館へ行きたいところだが、四国へ行くあてもなく
上野で見られるなら、それは便利かと思い、梅雨明けの空がキレイな上野へ
現代ものの彫刻は鑑賞が難しい、形は抽象化され、色彩に乏しい
どう向き合ったらいいのか戸惑う
「あかり」シリーズという和紙と針金でできた暖かく親しみのある照明を配置した心地良い空間を作り、そこに作品を並べることで、難解な彫刻への取っ付き難さはかなり抑えられている
そう、今回の展覧会の売りは、イサム・ノグチ空間を楽しむこと
圧巻は、最後の高松牟礼町の美術館を再現した、「牟礼の石彫」の部屋
コロナの人数制限のおかげで、ゆっくりとイサム・ノグチ空間に浸れて、幸せ
あ〜、やっぱり、高松の吹きっさらしの庭で観たい!
南陀楼綾繁という怪しげなペンネーム
失礼だけど、内澤旬子の元夫ということで知る人の方が多いかも、私もそうです(^^;
元奥さんもニッチな人だが、この人も負けず劣らず、ニッチです
そんな彼の本を2連発。実際に読んだのは3連発なんだけど、3冊目の新書は真面目でオタク的面白さに欠けたので、感想は省略
「蒐める人―情熱と執着のゆくえ」
本好き、それも古本好きマニアへのインタビュー集。読んでいると、聞いたことのない固有名詞がぽんぽん出てくるけど、うちわでは有名らしく、そのまま会話が弾んでゆく。オタクの会話集
「本のリストの本」
南陀楼氏を含めた5人の本好きオタクがリスト表を作って、語ってくれる。読み初めは、他の人が作ったリストの何が面白いと思っていたが、これがこれが、リスト表に詰まった選者の思い、これを選ぼう、あれも選ばないと、仕方ないけどこれは削るか的、ああでもない、こうでもない話が続いていて、読んでて飽きない
どちらの本も、毒にも薬にもならない話を、オタク的視線で、熱く語ってくれており、読んでる方もニヤニヤしてしまう。オタクにも歴史があり、彼らの熱い語りは、進化という偶然と必然のプロセスを経て出来上がった自然を記述した自然史的パースペクティブを感じる。オタクは創造主だ(なんのこっちゃ!)
失礼だけど、内澤旬子の元夫ということで知る人の方が多いかも、私もそうです(^^;
元奥さんもニッチな人だが、この人も負けず劣らず、ニッチです
そんな彼の本を2連発。実際に読んだのは3連発なんだけど、3冊目の新書は真面目でオタク的面白さに欠けたので、感想は省略
「蒐める人―情熱と執着のゆくえ」
本好き、それも古本好きマニアへのインタビュー集。読んでいると、聞いたことのない固有名詞がぽんぽん出てくるけど、うちわでは有名らしく、そのまま会話が弾んでゆく。オタクの会話集
「本のリストの本」
南陀楼氏を含めた5人の本好きオタクがリスト表を作って、語ってくれる。読み初めは、他の人が作ったリストの何が面白いと思っていたが、これがこれが、リスト表に詰まった選者の思い、これを選ぼう、あれも選ばないと、仕方ないけどこれは削るか的、ああでもない、こうでもない話が続いていて、読んでて飽きない
どちらの本も、毒にも薬にもならない話を、オタク的視線で、熱く語ってくれており、読んでる方もニヤニヤしてしまう。オタクにも歴史があり、彼らの熱い語りは、進化という偶然と必然のプロセスを経て出来上がった自然を記述した自然史的パースペクティブを感じる。オタクは創造主だ(なんのこっちゃ!)
ミステリーのベスト・オブ・ザ・イヤーが出ているのは知ってたけど
その文学版もあるらしい
文芸を生業とする者たちの職域団体である日本文藝家協会が編集しており
今回は、そのなかから短編文学のアンソロジー「文学2019」をチョイス
ちなみにこの文学××××、毎年出版されているらしく、××××には西暦が入る
気になって調べたら、遅くとも1974年には出てたらしい、ミステリーの方もこれぐらい古いのか!?
文学2019は、橋本治、村上春樹、多和田葉子、筒井康隆、松浦理恵子と贅沢な顔ぶれ
さらに、名前は聞いたことはあるけど、読んだことのなかった作家も入っており、その作家たちの作品が新鮮でしょうがなかった
その文学版もあるらしい
文芸を生業とする者たちの職域団体である日本文藝家協会が編集しており
今回は、そのなかから短編文学のアンソロジー「文学2019」をチョイス
ちなみにこの文学××××、毎年出版されているらしく、××××には西暦が入る
気になって調べたら、遅くとも1974年には出てたらしい、ミステリーの方もこれぐらい古いのか!?
文学2019は、橋本治、村上春樹、多和田葉子、筒井康隆、松浦理恵子と贅沢な顔ぶれ
さらに、名前は聞いたことはあるけど、読んだことのなかった作家も入っており、その作家たちの作品が新鮮でしょうがなかった
感想を書き逃した映画シリーズ、確かコロナ禍の渋谷で見たような
本気のしるし、深田晃司監督作
この監督さん、人の心の陰の部分を描くのが上手い印象がある
水の流れや踏切の警笛など、視覚イメージや音のイメージを使い、丁寧に人の心を描いてくれる。表からはもちろん、裏からも
この映画、大切なセリフは何度も繰り返される
元々はテレビドラマで30分10回分を、4時間に再編集したものらしい
というわけで、リフレインされるセリフを聴きながら、来週の展開やいかにというテレビ的ジェットコースターが繰り返される
「なんでこんなことしたんだよ」と責めるのに対して、「ごめんなさい」が繰り返され、山あり谷ありのジェットコースターに乗りながら、純愛へと昇華される
谷の別れるシーンでは、「君は十分に強い」とグッと刺さるフレーズが繰り返されるが、テレビドラマがハッピーエンドで終わらないわけがないと高を括って、安心してみられる
終わりに近い部分で、黄昏時、隣の部屋の人がかけるレコードで、ベートヴェン九番のアダージョが流れ、観ているものをホッとさせるも、もちろん次の谷は用意されてます
不自然に極端なキャラなどツッコミどころは満載だが、それを含めてドラマなんだと
テレビドラマを見なくなって十何年の身として、懐かしく楽しめた
ドラマっていいね!
本気のしるし、深田晃司監督作
この監督さん、人の心の陰の部分を描くのが上手い印象がある
水の流れや踏切の警笛など、視覚イメージや音のイメージを使い、丁寧に人の心を描いてくれる。表からはもちろん、裏からも
この映画、大切なセリフは何度も繰り返される
元々はテレビドラマで30分10回分を、4時間に再編集したものらしい
というわけで、リフレインされるセリフを聴きながら、来週の展開やいかにというテレビ的ジェットコースターが繰り返される
「なんでこんなことしたんだよ」と責めるのに対して、「ごめんなさい」が繰り返され、山あり谷ありのジェットコースターに乗りながら、純愛へと昇華される
谷の別れるシーンでは、「君は十分に強い」とグッと刺さるフレーズが繰り返されるが、テレビドラマがハッピーエンドで終わらないわけがないと高を括って、安心してみられる
終わりに近い部分で、黄昏時、隣の部屋の人がかけるレコードで、ベートヴェン九番のアダージョが流れ、観ているものをホッとさせるも、もちろん次の谷は用意されてます
不自然に極端なキャラなどツッコミどころは満載だが、それを含めてドラマなんだと
テレビドラマを見なくなって十何年の身として、懐かしく楽しめた
ドラマっていいね!