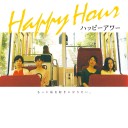この春は、いやこの春も、なんやかんや言いながら、やる気は起きず
武蔵野の片隅で、平静を装って生活してた
そんな時にハマったのがつげ義春、漫画もいいが、文章もいい
自然かつ、浮世離れしていながら、読んだ後にとりあえず前に進もうと思う
とりあえずね
次は内田百閒でも読むか
武蔵野の片隅で、平静を装って生活してた
そんな時にハマったのがつげ義春、漫画もいいが、文章もいい
自然かつ、浮世離れしていながら、読んだ後にとりあえず前に進もうと思う
とりあえずね
次は内田百閒でも読むか
美藤さんの日記で、内澤旬子さんが、あの名作「世界屠畜紀行」に続けて、本を出していることを知り、図書館で借りる
まずは「身体のいいなり」、病院通いのドタバタする様を曝け出すという意味で、山本文緒の「再婚生活 私のうつ闘病記」を思い出す
いろんな意味で女性って大変なのねと、男性の私は目から鱗を落としつつ、なんやかんや言いながらも、壁にぶつかりながらも、前へと進む彼女の指向性の強さがカッコ良い
本文中での親とパートナーの扱いがあまりにも酷くてちょっと痛い、でも私も似たようなものなので、他山の石にする
そのひどい扱いを受けている(あくまでも本の中でね)、元夫の編集者も本を出しているらしい。元夫婦揃って偏執なのだが、内澤さんのそれが他人が見たくなる明るい偏執なのに対して、元夫の偏執は暗くて本物らしい
怖いもの見たさに、元夫の本にも手を出そうかと
続いて「捨てる女」 古き自分を捨てて、新しき自分を発見する。要は、彼女の成長記であり、その過程が寄り道つきで面白い。そして自分の素をこれだけ曝け出せて、それを読み物として楽しませる彼女の才能はあらためて凄い
時系列として「飼い喰い」と重なり、彼女としても一番成長していた時期なのかと思ったけど、この本を読むと彼女の世界は小さい頃から少しずつ結晶化したものだとわかる。この後、小豆島への移住するらしく、そちらも読まねば
続いて「着せる女」、同じバブル経験者として、これからのお洒落はどこへ行くのかを知りたくて、内澤旬子さんのお洒落アンテナを探る
う〜ん、だめだった。彼女が売れて偉くなってしまったせいか、ちょっと遠くへ行ってしまった感を感じる。
口絵に彼女がコーデした知人のビフォー・アフターの写真が載っており、アフターは晴れの日のオシャレなドレスアップで決まってるけど、ビフォーのラフな格好はなんか残念でしょ、から本は始まる
服って着てて馴染んで来るんだよね、だから手持ちのラフな服もテロテロになりかかった頃が着ていて気持ちが良い。でも、テロテロ感は似合いすぎて、その人の素が全部見えすぎてしまい、装いとしてオシャレ感がなくて残念ということか
かつての捨てられない人だった彼女も素が一番のテロテロ派だと思ってたけど、「捨てる女」で変わった!?
3冊一気読みして満足、内澤旬子を本を通して追いかけてしまった
リアリティ番組にハマっているアメリカ人のようで、少し自分が気持ち悪い
少ししたら、島ものと、問題のストーカーものも読んでみます
まずは「身体のいいなり」、病院通いのドタバタする様を曝け出すという意味で、山本文緒の「再婚生活 私のうつ闘病記」を思い出す
いろんな意味で女性って大変なのねと、男性の私は目から鱗を落としつつ、なんやかんや言いながらも、壁にぶつかりながらも、前へと進む彼女の指向性の強さがカッコ良い
本文中での親とパートナーの扱いがあまりにも酷くてちょっと痛い、でも私も似たようなものなので、他山の石にする
そのひどい扱いを受けている(あくまでも本の中でね)、元夫の編集者も本を出しているらしい。元夫婦揃って偏執なのだが、内澤さんのそれが他人が見たくなる明るい偏執なのに対して、元夫の偏執は暗くて本物らしい
怖いもの見たさに、元夫の本にも手を出そうかと
続いて「捨てる女」 古き自分を捨てて、新しき自分を発見する。要は、彼女の成長記であり、その過程が寄り道つきで面白い。そして自分の素をこれだけ曝け出せて、それを読み物として楽しませる彼女の才能はあらためて凄い
時系列として「飼い喰い」と重なり、彼女としても一番成長していた時期なのかと思ったけど、この本を読むと彼女の世界は小さい頃から少しずつ結晶化したものだとわかる。この後、小豆島への移住するらしく、そちらも読まねば
続いて「着せる女」、同じバブル経験者として、これからのお洒落はどこへ行くのかを知りたくて、内澤旬子さんのお洒落アンテナを探る
う〜ん、だめだった。彼女が売れて偉くなってしまったせいか、ちょっと遠くへ行ってしまった感を感じる。
口絵に彼女がコーデした知人のビフォー・アフターの写真が載っており、アフターは晴れの日のオシャレなドレスアップで決まってるけど、ビフォーのラフな格好はなんか残念でしょ、から本は始まる
服って着てて馴染んで来るんだよね、だから手持ちのラフな服もテロテロになりかかった頃が着ていて気持ちが良い。でも、テロテロ感は似合いすぎて、その人の素が全部見えすぎてしまい、装いとしてオシャレ感がなくて残念ということか
かつての捨てられない人だった彼女も素が一番のテロテロ派だと思ってたけど、「捨てる女」で変わった!?
3冊一気読みして満足、内澤旬子を本を通して追いかけてしまった
リアリティ番組にハマっているアメリカ人のようで、少し自分が気持ち悪い
少ししたら、島ものと、問題のストーカーものも読んでみます
クールベと海展@汐留
2021年6月4日 日常
コロナのせいで、ご無沙汰になっていた美術館
再開されたら何から行こうかと悩んでいたが、日本であまり紹介されてこなかったことが話題のクールベを見に汐留へ
そう言えば、汐留のパナソニック本社のなかにあるこの美術館、初めてかも
新橋の駅なかを延々歩いてたどり着いたのは、味もそっけもないビルのなか
美術館がビルのなかにあるのは珍しくないし、サントリー・出光・ブリヂストンなどは、それぞれ独特のデザインで、非日常の空間である美術館という器をビルのなかに出現させて、建物に入った瞬間ワクワクする
汐留のパナは、かつてのデパートの催事場を思わせる空間で、少し味気ない
実はこの展覧会、ミレーで有名な山梨県立美術館の小ぶりな企画「クールベと海展」の巡回展で
山梨では昨年開かれており、山登りのついでに、海なし県山梨でマイナーな画家の海景画展を見にくのも良いなと思ってた
それがコロナで機会を逃し…
そしたら、コロナ自粛中、彼を紹介するテレビを見ていて
クールベは、近世の宗教画を超越した、写実主義の先駆者であり、のちに現れる世界のモネに影響を与えたという点では、西洋美術史では重要な人物であるらしい。知らなかった!
すっかりテレビでクールベの偉大さを刷り込まれて…
実は実は、テレビで紹介されていた絵画史におけるクールベの偉大さは、小さな海景画が並べたこの企画とはあまり関係なく、テレビで紹介されていたような大作の歴史画は来ていない。だから「クールベ展」ではなく、「クールベと海展」なのね、看板に偽りなし
勝手に思い込んだ私が悪い
というわけで、クールベの偉大さが伝わってくる展覧会ではないし
ビルの中の催事場のような空間だし
それにコロナもまだ収束してないけど
久々に展覧会へ行けたことに満足
汐留という地名には汐が入ってるけど、山梨と同じく海感まったくなし
再開されたら何から行こうかと悩んでいたが、日本であまり紹介されてこなかったことが話題のクールベを見に汐留へ
そう言えば、汐留のパナソニック本社のなかにあるこの美術館、初めてかも
新橋の駅なかを延々歩いてたどり着いたのは、味もそっけもないビルのなか
美術館がビルのなかにあるのは珍しくないし、サントリー・出光・ブリヂストンなどは、それぞれ独特のデザインで、非日常の空間である美術館という器をビルのなかに出現させて、建物に入った瞬間ワクワクする
汐留のパナは、かつてのデパートの催事場を思わせる空間で、少し味気ない
実はこの展覧会、ミレーで有名な山梨県立美術館の小ぶりな企画「クールベと海展」の巡回展で
山梨では昨年開かれており、山登りのついでに、海なし県山梨でマイナーな画家の海景画展を見にくのも良いなと思ってた
それがコロナで機会を逃し…
そしたら、コロナ自粛中、彼を紹介するテレビを見ていて
クールベは、近世の宗教画を超越した、写実主義の先駆者であり、のちに現れる世界のモネに影響を与えたという点では、西洋美術史では重要な人物であるらしい。知らなかった!
すっかりテレビでクールベの偉大さを刷り込まれて…
実は実は、テレビで紹介されていた絵画史におけるクールベの偉大さは、小さな海景画が並べたこの企画とはあまり関係なく、テレビで紹介されていたような大作の歴史画は来ていない。だから「クールベ展」ではなく、「クールベと海展」なのね、看板に偽りなし
勝手に思い込んだ私が悪い
というわけで、クールベの偉大さが伝わってくる展覧会ではないし
ビルの中の催事場のような空間だし
それにコロナもまだ収束してないけど
久々に展覧会へ行けたことに満足
汐留という地名には汐が入ってるけど、山梨と同じく海感まったくなし
感想を書き逃した映画
中国では新しい才能あふれる映画監督が筍のように次から次へ出てきて、日本のお笑いタレントのように、中国映画監督第〇世代とカテゴライズされているらしい
この作品の監督ディアオ・イーナンは第六世代、「ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ」のビー・ガン監督は第八世代らしいが、国際映画祭の常連も多く、もう中国映画というくくりを超えてるような
この作品、娯楽性あり、社会性もあり、かつ情をあつかい、そしてカタルシスもある。勢いのある国の映画は、その国を好む好まないは置いといて、観て楽しい
中国では新しい才能あふれる映画監督が筍のように次から次へ出てきて、日本のお笑いタレントのように、中国映画監督第〇世代とカテゴライズされているらしい
この作品の監督ディアオ・イーナンは第六世代、「ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ」のビー・ガン監督は第八世代らしいが、国際映画祭の常連も多く、もう中国映画というくくりを超えてるような
この作品、娯楽性あり、社会性もあり、かつ情をあつかい、そしてカタルシスもある。勢いのある国の映画は、その国を好む好まないは置いといて、観て楽しい
ペドロ・コスタ監督の「ヴィタリナ」を観る
このポルトガル人監督さんの作品は素晴らしいが、娯楽性、商業性に欠けており、日本では滅多に上映されない
最近読んだ本、「リスボンへの夜行列車」とはリスボンつながり、さらに「オルガ」とはアフリカの植民地つながり
主人公は、リスボンへ出稼ぎに出ている夫が危篤との知らせを受け、ポルトガルの旧植民地カボ・ヴェルデからリスボンに出てくる。しかし、夫の死に目に会えず仕舞い。
誰も身寄りのない彼女の、にっちもさっちも行かない状況が陽が当たらない闇のシーンとして、BGMなしで、延々と描かれている
そして、最後の最後に陽のあたる明るい画面が少し出てくる
「オルガ」同様、近代の発展は誰かの犠牲の上になっており、犠牲になったものたちは現代も救われないままという残酷さを教えてくれる。最後、彼女が少し女神に見えたのが少しの救いだけど、私の勘違いか、実ることのない希望なのかもしれない
このポルトガル人監督さんの作品は素晴らしいが、娯楽性、商業性に欠けており、日本では滅多に上映されない
最近読んだ本、「リスボンへの夜行列車」とはリスボンつながり、さらに「オルガ」とはアフリカの植民地つながり
主人公は、リスボンへ出稼ぎに出ている夫が危篤との知らせを受け、ポルトガルの旧植民地カボ・ヴェルデからリスボンに出てくる。しかし、夫の死に目に会えず仕舞い。
誰も身寄りのない彼女の、にっちもさっちも行かない状況が陽が当たらない闇のシーンとして、BGMなしで、延々と描かれている
そして、最後の最後に陽のあたる明るい画面が少し出てくる
「オルガ」同様、近代の発展は誰かの犠牲の上になっており、犠牲になったものたちは現代も救われないままという残酷さを教えてくれる。最後、彼女が少し女神に見えたのが少しの救いだけど、私の勘違いか、実ることのない希望なのかもしれない
「朗読者」で有名なベルンハルト・シュリンクの小説
この前に読んだ「リスボン…」とは、ドイツ語で書かれた小説つながり
さらに、どちらも、近代の困難な状況下で生きた他人の謎を、主人公のおじさんが追いかける体を取っている。
「リスボン」では、主人公の古文の先生が古本屋でたまたま手にした私家版の本を通してリスボンの医師の人生の謎解きにのぞみ、「オルガ」では主人公の男性が骨董屋さんでなんとか手に入れたノルウェーのトロムソ局留めの手紙を通してポーランド系ドイツ人女性オルガの人生の謎解きがのぞむ
よく言われることだが、困難な状況下で一番被害を被るのは立場の弱い女性や子供であると
この小説でも、オルガという女性が、遅れてきたドイツ人が強国の一員になる夢に浮かれていたドイツ帝国時代、ナチスの独裁時代、戦後の東西に分断された時代を通して、ものも言わずに、いや、ものを言えずに耐え忍んだ行く末が描かれている
同時代に生きた人でも、「リスボン」のお医者さんにはロマンが残り、スラブ人によくある名前の女性オルガには不条理が残る
ただ、オルガに希望がないかと言えばそうでもなく、「リスボン」と同じく、主人公の男性が、困難な時代を過ごしたオルガの人生から覇気をもらい、それを読んで私も少しの覇気をもらう
この前に読んだ「リスボン…」とは、ドイツ語で書かれた小説つながり
さらに、どちらも、近代の困難な状況下で生きた他人の謎を、主人公のおじさんが追いかける体を取っている。
「リスボン」では、主人公の古文の先生が古本屋でたまたま手にした私家版の本を通してリスボンの医師の人生の謎解きにのぞみ、「オルガ」では主人公の男性が骨董屋さんでなんとか手に入れたノルウェーのトロムソ局留めの手紙を通してポーランド系ドイツ人女性オルガの人生の謎解きがのぞむ
よく言われることだが、困難な状況下で一番被害を被るのは立場の弱い女性や子供であると
この小説でも、オルガという女性が、遅れてきたドイツ人が強国の一員になる夢に浮かれていたドイツ帝国時代、ナチスの独裁時代、戦後の東西に分断された時代を通して、ものも言わずに、いや、ものを言えずに耐え忍んだ行く末が描かれている
同時代に生きた人でも、「リスボン」のお医者さんにはロマンが残り、スラブ人によくある名前の女性オルガには不条理が残る
ただ、オルガに希望がないかと言えばそうでもなく、「リスボン」と同じく、主人公の男性が、困難な時代を過ごしたオルガの人生から覇気をもらい、それを読んで私も少しの覇気をもらう
リスボンへの夜行列車
2021年3月30日 日常 コメント (2)
ジェレミー・アイアンズ主演映画の原作ということで、ずっと気になっていたが、未読リストに埋もれていた。
数ヶ月前、日記仲間のhanaさんのところで、リスボンと言う文字を見つけたことが転機となり、私は主人公とともに列車でリスボンへ向かうことになる
読者であるおじさんの私、ベルンの高校で古典の先生をしている主人公のおじさん、主人公がふとしたきっかけで興味を持ったポルトガルの困難な時代を生きたお医者さんのおじさんの、おじさん3人の揃い踏み。
主人公のおじさんはポルトガル人医師の人生を追いかけ、読者の私は主人公のおじさんの人生を追けかける。人生は線路のようにいくつかのポイントを通過しながら、一本の線としてつながり、さらに大切な人の人生と交差をしながら覚醒することもあれば、戻ることはできないポイントにめまいを感じる。でも線路は続くよ
主人公の古典の先生は、独裁時代の困難な状況下で生きたポルトガル人医師の人生を通して、人間は尊厳をどう守るべきかという壮大なテーマが存在した時代がかつてあったことを知り、自分の線路を進むべく覇気をもらう。そして、現代のぬるま湯の時代に過ごしている私は覚醒した主人公から少し覇気を分けてもらう
3人とも不眠症になまされており、世代は違えど共感を覚える
「薔薇の名前」を好きな人におすすめ
数ヶ月前、日記仲間のhanaさんのところで、リスボンと言う文字を見つけたことが転機となり、私は主人公とともに列車でリスボンへ向かうことになる
読者であるおじさんの私、ベルンの高校で古典の先生をしている主人公のおじさん、主人公がふとしたきっかけで興味を持ったポルトガルの困難な時代を生きたお医者さんのおじさんの、おじさん3人の揃い踏み。
主人公のおじさんはポルトガル人医師の人生を追いかけ、読者の私は主人公のおじさんの人生を追けかける。人生は線路のようにいくつかのポイントを通過しながら、一本の線としてつながり、さらに大切な人の人生と交差をしながら覚醒することもあれば、戻ることはできないポイントにめまいを感じる。でも線路は続くよ
主人公の古典の先生は、独裁時代の困難な状況下で生きたポルトガル人医師の人生を通して、人間は尊厳をどう守るべきかという壮大なテーマが存在した時代がかつてあったことを知り、自分の線路を進むべく覇気をもらう。そして、現代のぬるま湯の時代に過ごしている私は覚醒した主人公から少し覇気を分けてもらう
3人とも不眠症になまされており、世代は違えど共感を覚える
「薔薇の名前」を好きな人におすすめ
毎年、冬から春の季節の変わり目になると調子が悪くなる
過去の日記を読み返すと、冷え性、肩こり、頭痛、不眠がおもな症状で、ここ10年ほど悩まされているらしい
日記を読み返すと、忘れていた自分を知ることができ便利
去年からジム通いを再開し、運動をするようになったせいか、頭痛は無くなる
頭痛がないと鎮痛剤を飲まなくても済むので、鎮痛剤による胃痛もなくなる
ひとつ減っただけでだいぶ安心できる
まだ、肩こりと冷え性はあるが、それも温かいものを適度に取り、ストレッチをすることで、ましになり、対処法を知っているとかなり安心できる
今年はコロナのせいで、換気がしっかりなされており、電車、映画館、美術館、どこへ行っても寒い。サーモスに入れたハーブティーを飲みながら、肩甲骨を回す
不眠は辛いが、処方してもらっている薬を飲めば寝付けるので、こちらも安心。明け方に目覚めてしまい、午前中頭にモヤがかかったままになることもあるが、気分だけでも揚げようと、眉間にシワを寄せないように気をつける。人間単純なもので、これが割と効くもんだ
過去の日記を読み返すと、冷え性、肩こり、頭痛、不眠がおもな症状で、ここ10年ほど悩まされているらしい
日記を読み返すと、忘れていた自分を知ることができ便利
去年からジム通いを再開し、運動をするようになったせいか、頭痛は無くなる
頭痛がないと鎮痛剤を飲まなくても済むので、鎮痛剤による胃痛もなくなる
ひとつ減っただけでだいぶ安心できる
まだ、肩こりと冷え性はあるが、それも温かいものを適度に取り、ストレッチをすることで、ましになり、対処法を知っているとかなり安心できる
今年はコロナのせいで、換気がしっかりなされており、電車、映画館、美術館、どこへ行っても寒い。サーモスに入れたハーブティーを飲みながら、肩甲骨を回す
不眠は辛いが、処方してもらっている薬を飲めば寝付けるので、こちらも安心。明け方に目覚めてしまい、午前中頭にモヤがかかったままになることもあるが、気分だけでも揚げようと、眉間にシワを寄せないように気をつける。人間単純なもので、これが割と効くもんだ
ハニーランド 永遠の谷
2021年2月9日 日常
こちらは見逃した映画ではなく、感想を書き逃した映画
何か書きたいんだけど、映画を観た直後は気落ちがまとまらなくて、こうしてしばらく時間を空けると、いい映画だったなと見直せることも
ハチミツは世界中どこの国へ行っても、ファーマーズマーケットで必ず並んでるいる定番商品。それだけハチミツは世界中で愛されているということか
そんなハチミツを集めてくれるミツバチの映画と言えば、ビクトル・エリセの「ミツバチのささやき」。主人公の少女のお父さんが趣味で(?)養蜂するミツバチの羽音が心地よい映画
トルコ映画の「蜂蜜」は。主人公の少年のお父さんが野生の蜂蜜採りを生業にしているマタギのような方で、森に棲む野生のミツバチの羽音が勇ましい
そして、新たなミツバチ映画、北マケドニアの「ハニーランド永遠の谷」では主人公の蜜蜂名人のおばさんが野生の蜜蜂を集めるときに掛ける「ほーい、ほーい」という声が、ミツバチの羽音に劣らずかっこいい
どの映画でも、ニュアンスは違うものの、ミツバチは人間が現れる前から存在する原自然の象徴として描かれており、「ささやき」の神聖さ、「ハニーランド」の自然の恵み、「蜜蜂」ではちょうど両者の中間的なものが映画に良いエッセンスを加える
さて、北マケドニア映画の「ハニーランド永遠の谷」は、行き過ぎた文明を諫める自然讃歌の映画として、ほっこりさせてくれるかというと、そんなに甘くはない。マケドニア人は、小国北マケドニアとして今でこそ独立しているが、周辺の強国、ギリシャ、トルコ、セルビアに、隙あらば攻められ、支配され続けた悲しい歴史がある
映画には、彼らのうちトルコ人が悪者役で出てくる
主人公のおばさんは、野生のミツバチの巣を見つけると半分は自然からのお裾分けとしてもらうが、半分は残し、持続可能な自然となるように心がけている
隣に越してきた、ちょっと粗暴なトルコ人家族は、そんな主人公の心がけなどお構いなく、現金収入のため、環境収容力以上の巣箱をおいたり、野生のミツバチを巣ごと収穫したりし、主人公が大切に育ててきた里山的半自然をあっけなく壊していしまう
もちろんトルコ人のお父さんは雑な人だが、全然悪気はなく、沢山の子供を養わないといけないという事情があることもわかる
しかし自然を破壊する悪者役を、憎くきオスマントルコの末裔に押し付けるキャスティングには悪意を感じなくもなく、北マケドニア人の恨みつらみを感じる
ただ、人間である限り、歴史から逃れることができないメタファーとしてトルコ人がキャスティングされているだけであり、それほど悪意も恨みもないのかも
バルカン半島の事情に、北マケドニアの現状に詳しくない私には判断しかねる
でも、「朝焼け」と「焚き火の火」は、国境と関係なく、世界中どこへ行っても美しいことに感動できます
何か書きたいんだけど、映画を観た直後は気落ちがまとまらなくて、こうしてしばらく時間を空けると、いい映画だったなと見直せることも
ハチミツは世界中どこの国へ行っても、ファーマーズマーケットで必ず並んでるいる定番商品。それだけハチミツは世界中で愛されているということか
そんなハチミツを集めてくれるミツバチの映画と言えば、ビクトル・エリセの「ミツバチのささやき」。主人公の少女のお父さんが趣味で(?)養蜂するミツバチの羽音が心地よい映画
トルコ映画の「蜂蜜」は。主人公の少年のお父さんが野生の蜂蜜採りを生業にしているマタギのような方で、森に棲む野生のミツバチの羽音が勇ましい
そして、新たなミツバチ映画、北マケドニアの「ハニーランド永遠の谷」では主人公の蜜蜂名人のおばさんが野生の蜜蜂を集めるときに掛ける「ほーい、ほーい」という声が、ミツバチの羽音に劣らずかっこいい
どの映画でも、ニュアンスは違うものの、ミツバチは人間が現れる前から存在する原自然の象徴として描かれており、「ささやき」の神聖さ、「ハニーランド」の自然の恵み、「蜜蜂」ではちょうど両者の中間的なものが映画に良いエッセンスを加える
さて、北マケドニア映画の「ハニーランド永遠の谷」は、行き過ぎた文明を諫める自然讃歌の映画として、ほっこりさせてくれるかというと、そんなに甘くはない。マケドニア人は、小国北マケドニアとして今でこそ独立しているが、周辺の強国、ギリシャ、トルコ、セルビアに、隙あらば攻められ、支配され続けた悲しい歴史がある
映画には、彼らのうちトルコ人が悪者役で出てくる
主人公のおばさんは、野生のミツバチの巣を見つけると半分は自然からのお裾分けとしてもらうが、半分は残し、持続可能な自然となるように心がけている
隣に越してきた、ちょっと粗暴なトルコ人家族は、そんな主人公の心がけなどお構いなく、現金収入のため、環境収容力以上の巣箱をおいたり、野生のミツバチを巣ごと収穫したりし、主人公が大切に育ててきた里山的半自然をあっけなく壊していしまう
もちろんトルコ人のお父さんは雑な人だが、全然悪気はなく、沢山の子供を養わないといけないという事情があることもわかる
しかし自然を破壊する悪者役を、憎くきオスマントルコの末裔に押し付けるキャスティングには悪意を感じなくもなく、北マケドニア人の恨みつらみを感じる
ただ、人間である限り、歴史から逃れることができないメタファーとしてトルコ人がキャスティングされているだけであり、それほど悪意も恨みもないのかも
バルカン半島の事情に、北マケドニアの現状に詳しくない私には判断しかねる
でも、「朝焼け」と「焚き火の火」は、国境と関係なく、世界中どこへ行っても美しいことに感動できます
2021年、見逃した映画第二弾
みなさんの日記に、いい作品だと書いてあって、ずっと気になっていた作品
副題に、「優しい歌」とあるように、優しい映画です
世界が寛容さを失いかけているこの時代だからこそ、愛(恋人同志の、家族の、そして神様の愛)と音楽に包まれた優しい映画が良いんだと思う
あまりにも良い映画で、内容について僕の下手な文章で言うことはありません
見てくださいと、すべての人にススメたくなる映画
映画はタレンタイムという学校主催の音楽コンテストが舞台。コンテストで演奏される音楽も良いんだけど、BGMで流れるゴルトベルクと月の光がまた心地良い
ドビュッシーの月の光と言えば、岩井俊二の「リリィ・シュシュのすべて」が思い浮かぶ。その岩井俊二の「ラストレター」も見逃した映画リストに残ったまま。四月物語の松たか子、好きだったんだよな。20年振りに岩井俊二映像の松たか子が楽しめると考えただけでワクワクする。どこかでやんないかな〜
みなさんの日記に、いい作品だと書いてあって、ずっと気になっていた作品
副題に、「優しい歌」とあるように、優しい映画です
世界が寛容さを失いかけているこの時代だからこそ、愛(恋人同志の、家族の、そして神様の愛)と音楽に包まれた優しい映画が良いんだと思う
あまりにも良い映画で、内容について僕の下手な文章で言うことはありません
見てくださいと、すべての人にススメたくなる映画
映画はタレンタイムという学校主催の音楽コンテストが舞台。コンテストで演奏される音楽も良いんだけど、BGMで流れるゴルトベルクと月の光がまた心地良い
ドビュッシーの月の光と言えば、岩井俊二の「リリィ・シュシュのすべて」が思い浮かぶ。その岩井俊二の「ラストレター」も見逃した映画リストに残ったまま。四月物語の松たか子、好きだったんだよな。20年振りに岩井俊二映像の松たか子が楽しめると考えただけでワクワクする。どこかでやんないかな〜
プラド美術館 驚異のコレクション
2021年1月25日 日常 コメント (4)
高校の美術の先生が、芸術を楽しむならパリも良いけど、スペインかギリシャへ行ってみなさい。洗練された芸術はないけど、土着の美に溢れているからと教えてくれた
その言葉がずっと頭に残っていて、大学生の時に、スペインとギリシャで美術館巡りをして、楽しかった思い出がある。
スペインへ行ったのは二十歳のころ
まだ若かった私には、プラド美術館本館の良さはあまり分からず、当時プラドの別館だったピカソのゲルニカ館の印象の方が強かった
その馴染みゆえ、日本でスペイン関連の絵画展が開催されると必ず通うように、そして本館のスターたち、レンブラント、ベラスケス、ゴヤの良さが歳とともにわかるようになってきた
この映画、そんなプラドの絵画を、我らが世代の伊達男、ジェレミー・アイアンズが案内してくれる。歳とったけど、まだまだイケてる
でも、我らが日本の伊達男、「美の壷」の草刈正雄には負けるな
その言葉がずっと頭に残っていて、大学生の時に、スペインとギリシャで美術館巡りをして、楽しかった思い出がある。
スペインへ行ったのは二十歳のころ
まだ若かった私には、プラド美術館本館の良さはあまり分からず、当時プラドの別館だったピカソのゲルニカ館の印象の方が強かった
その馴染みゆえ、日本でスペイン関連の絵画展が開催されると必ず通うように、そして本館のスターたち、レンブラント、ベラスケス、ゴヤの良さが歳とともにわかるようになってきた
この映画、そんなプラドの絵画を、我らが世代の伊達男、ジェレミー・アイアンズが案内してくれる。歳とったけど、まだまだイケてる
でも、我らが日本の伊達男、「美の壷」の草刈正雄には負けるな
掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集
2021年1月18日 日常
昨年、日本でも話題になった、忘れられていたアメリカ人作家の短編集
1970年代、ソビエト連邦がまだまだ元気で、ちょうど冷戦真っ只なかの時代
世代的には、ビートジェネレーションのあとのカウンターカルチャーに当たるんだろうけど、ぶっ飛び感はビートジェネレーションらしく、自然体はカウンターカルチャーらしく、既存の分類の型にはハマりきらない新鮮さがよろしい
フィクションと自伝が入り交じったリアルの果てのシュールレアリズムの世界を楽しめる
1970年代、ソビエト連邦がまだまだ元気で、ちょうど冷戦真っ只なかの時代
世代的には、ビートジェネレーションのあとのカウンターカルチャーに当たるんだろうけど、ぶっ飛び感はビートジェネレーションらしく、自然体はカウンターカルチャーらしく、既存の分類の型にはハマりきらない新鮮さがよろしい
フィクションと自伝が入り交じったリアルの果てのシュールレアリズムの世界を楽しめる
ハッピーアワー@シアター・イメージフォーラム
2021年1月15日 日常 コメント (2)
ずっと観たかった濱口竜介監督のハッピーアワーが年末年始にリバイバル上映されるのをネットでたまたま発見
この監督さん、この作品で評価されて、3年後に「寝ても覚めても」で商業映画デビュー、どちらも見逃した映画のまま
コロナの新規感染者の伸びが止まらず、映画館へ出かけることに気が引けたが、ここで見逃したら、もう出会えないかもと思い、大晦日の渋谷へ
脚本を担当した「スパイの妻」も見逃しそう
5年前の作品で、上映時間6時間という長さで少し話題に
市民参加の「即興演技ワークショップ」から誕生したという特殊な作品で商業作品ではない
映画の専門教育を受け、映像関連の職について、趣味の域を超えたドキュメンタリー映画をとっており、映画の玄人と言える監督さんに手を引っ張られて、演技のワークショップに参加して、もっと表現活動をしてみたいと思った素人役者たちが自己表現を楽しむ過程が編集されている。そのあたりの事情も理解して鑑賞すると、なかなか面白く、観ている側もとても楽しめる。
内容は30代女性が抱える様々な事情を、群像劇で表現した映像作品だが、上でも言ったように、そして下もで書くように、それ以上でも、それ以下でもない
素人役者さんたちは、自分のセリフを悩みに悩んで決めたらしい、口から出てくるセリフに愛着が感じられる。ただ演技を仕込むまでの時間も手間もなかったらしく、セリフはほぼ棒読み状態。台本のある即興演技を目指しており(?)、演出された演技はなく、そこも新鮮でよろしい
主人公の女性たちが抱えている事情があまりにも十人十色であるため、頭が混乱しそうになるが、その多様ぶりの中で、「自分」探しがテーマで、自分らしくていいんだよという、ありきたりなメッセージが伝わってくる
でも孤独な「自分」は、自分が他人に理解されるなんてことは決してないと知っていながら、理解してもらえる友人という幻想に振り回され、他人が友人になったり、友人が他人になったりすることがあり、これまた忙しい
結局は、個人に属するものが優先されない日本特有の息苦しさと、社会の中で僕たちは「自分」を演じなければいけないという不自由さに行き着く
…のようなことがメビウスの輪のように頭のなかでぐるぐる廻るうちに、作品のメッセージを必死に読み解こうとする自分が嘘っっぽく感じて、結局は映画を捨てて街に出て、「自分」を演じようという前向きな気持ちにさせくれる
映画館をあとにしたのが19時過ぎ、あと5時間ほどで年が明ける
大晦日のスクランブル交差点閉鎖のため、青山通りで待機している機動隊の集団に遭遇して、コロナの世界に戻される
この監督さん、この作品で評価されて、3年後に「寝ても覚めても」で商業映画デビュー、どちらも見逃した映画のまま
コロナの新規感染者の伸びが止まらず、映画館へ出かけることに気が引けたが、ここで見逃したら、もう出会えないかもと思い、大晦日の渋谷へ
脚本を担当した「スパイの妻」も見逃しそう
5年前の作品で、上映時間6時間という長さで少し話題に
市民参加の「即興演技ワークショップ」から誕生したという特殊な作品で商業作品ではない
映画の専門教育を受け、映像関連の職について、趣味の域を超えたドキュメンタリー映画をとっており、映画の玄人と言える監督さんに手を引っ張られて、演技のワークショップに参加して、もっと表現活動をしてみたいと思った素人役者たちが自己表現を楽しむ過程が編集されている。そのあたりの事情も理解して鑑賞すると、なかなか面白く、観ている側もとても楽しめる。
内容は30代女性が抱える様々な事情を、群像劇で表現した映像作品だが、上でも言ったように、そして下もで書くように、それ以上でも、それ以下でもない
素人役者さんたちは、自分のセリフを悩みに悩んで決めたらしい、口から出てくるセリフに愛着が感じられる。ただ演技を仕込むまでの時間も手間もなかったらしく、セリフはほぼ棒読み状態。台本のある即興演技を目指しており(?)、演出された演技はなく、そこも新鮮でよろしい
主人公の女性たちが抱えている事情があまりにも十人十色であるため、頭が混乱しそうになるが、その多様ぶりの中で、「自分」探しがテーマで、自分らしくていいんだよという、ありきたりなメッセージが伝わってくる
でも孤独な「自分」は、自分が他人に理解されるなんてことは決してないと知っていながら、理解してもらえる友人という幻想に振り回され、他人が友人になったり、友人が他人になったりすることがあり、これまた忙しい
結局は、個人に属するものが優先されない日本特有の息苦しさと、社会の中で僕たちは「自分」を演じなければいけないという不自由さに行き着く
…のようなことがメビウスの輪のように頭のなかでぐるぐる廻るうちに、作品のメッセージを必死に読み解こうとする自分が嘘っっぽく感じて、結局は映画を捨てて街に出て、「自分」を演じようという前向きな気持ちにさせくれる
映画館をあとにしたのが19時過ぎ、あと5時間ほどで年が明ける
大晦日のスクランブル交差点閉鎖のため、青山通りで待機している機動隊の集団に遭遇して、コロナの世界に戻される
オフィスのデスク脇の本棚に私物のカレンダーを掛けている
一応職場で他の人の目にも触れるので、無難で王道ものが多く、ポール・セザンヌの静物画やクロード・モネの風景画といったところを選ぶ
ちょっと刺激が欲しい年は、ジョージア・オキーフやメープル・ソープの花シリーズとか、世紀末のグスタフ・クリムト、さらにはビビッドなゴッホだったり
2016年は、アメリカ人画家エドワード・ホッパーを選んだ
王道さも、ビビッドさもないが、アメリカらしい太陽に満ちた開けた空間が描かれていて、オフィスの窓から見える東京のせせこましさを補ってくれていた
そんなホッパーの絵をもとにインスパイアーされた短編集のアンソロジー作品「短編画廊」を読む。ホッパーの絵と別々の現代アメリカ人作家の短編小説がセットになって並んでいる
5年前のオフィスに飾っていたカレンダーと重なっている絵は1つだけ、それも担当するはずだった作家が小説を書けなかったという理由で、小説抜きで口絵に使われている“Cape Cod Morning”
オフィスのカレンダーのホッパーは無難な風景画が多く、青空のもと広大な自然が広がっているが、必ず人や建物といった人間の営みが描きこまれているのがホッパーらしい
一方で、この短編画廊で選ばれているホッパーは、街頭に照らされた夜の街、屋内、建物の外から窓を通して描かれた室内など、自然の比率がグッと下がり、孤独感漂う人の営み中心に描かれている作品が多い、やはりホッパーらしい
というわけで、孤独感あふれる人々の物語が楽しめます
ちなみに、来年は出入りの業者にもらった白地のカレンダー
一応職場で他の人の目にも触れるので、無難で王道ものが多く、ポール・セザンヌの静物画やクロード・モネの風景画といったところを選ぶ
ちょっと刺激が欲しい年は、ジョージア・オキーフやメープル・ソープの花シリーズとか、世紀末のグスタフ・クリムト、さらにはビビッドなゴッホだったり
2016年は、アメリカ人画家エドワード・ホッパーを選んだ
王道さも、ビビッドさもないが、アメリカらしい太陽に満ちた開けた空間が描かれていて、オフィスの窓から見える東京のせせこましさを補ってくれていた
そんなホッパーの絵をもとにインスパイアーされた短編集のアンソロジー作品「短編画廊」を読む。ホッパーの絵と別々の現代アメリカ人作家の短編小説がセットになって並んでいる
5年前のオフィスに飾っていたカレンダーと重なっている絵は1つだけ、それも担当するはずだった作家が小説を書けなかったという理由で、小説抜きで口絵に使われている“Cape Cod Morning”
オフィスのカレンダーのホッパーは無難な風景画が多く、青空のもと広大な自然が広がっているが、必ず人や建物といった人間の営みが描きこまれているのがホッパーらしい
一方で、この短編画廊で選ばれているホッパーは、街頭に照らされた夜の街、屋内、建物の外から窓を通して描かれた室内など、自然の比率がグッと下がり、孤独感漂う人の営み中心に描かれている作品が多い、やはりホッパーらしい
というわけで、孤独感あふれる人々の物語が楽しめます
ちなみに、来年は出入りの業者にもらった白地のカレンダー
今年の夏は、心と体のバランスが悪く、酷く疲れることが多々
もう、頭も体も動きませんという状態に追い詰められそうに何度もなる
以前、うつで休職を体験していて、その時の通院経験から、対処法はそれなりに習得していて、なんとかなっている
対処法と言ったって、所詮は誤魔化しでしかなく、休むが一番
ということで、今年の夏以降は時間を作ってはサボってます
けど、いろんなところで聞くけど、この休むことが一番難しい。逆に、休めるのはまだ調子が悪くない証拠と思ってしまう
調子が悪いと休むことがままならない
夏場も過ぎて、だいぶ落ち着き、読書でも始めるかと思ったときに、手に取ったのが心の病がらみの本2冊、さらに落ち着いてきた冬、思い出しながら感想を
最相葉月のセラピスト、日本の心理学の巨人、河合隼雄が日本に広めた心理療法の一種、箱庭療法の話から入り、セラピスト、今の心理療法士と言う職業の歴史について淡々と語っている。彼女の文章は丁寧で誠実で、読んでいて落ち着く
そして、衝撃のカミングアウト、でも彼女はあまり騒ぎ立てない
最後、人間とは?、社会のなかの人間とは?と言う根源的なテーマに向かい、色々あっていいんだよという優しい雰囲気で本は終わる
うん、人間、コミュニケーションが大事だなと納得。
私も小さい頃、コミュニケーションが苦手で、そのまま人と関わらない仕事に就きたいと思っていた。たまたま運良く、ひとり気ままでワガママを押し通せる職に就いてしまった。この若い時に苦労しなかったことのしっぺ返しがこの歳でブーメランのように自分に帰ってきたと思っている
もう一冊は、山本文緒の「再婚生活 私のうつ闘病日記」
こちら、うつを患った著者の痛い話
さすが直木賞作家、痛いを描かせるとうまい。うつを患っている著者はこれでもかと大袈裟に騒ぎ立てる。これは演出かと疑うが、ありのままの壮絶なうつ日記らしい。あとがきの書き手は別人かと思うほど落ち着き払っており、治るってこういうことかと納得。そして、さすが作家、その言葉に勇気をもらう
今年もあと少し、世間も私もあまり良くなかった年だったかもしれないが
良い悪いは別にして、こんな年もある
まるで論語の世界に入りつつある
もう、頭も体も動きませんという状態に追い詰められそうに何度もなる
以前、うつで休職を体験していて、その時の通院経験から、対処法はそれなりに習得していて、なんとかなっている
対処法と言ったって、所詮は誤魔化しでしかなく、休むが一番
ということで、今年の夏以降は時間を作ってはサボってます
けど、いろんなところで聞くけど、この休むことが一番難しい。逆に、休めるのはまだ調子が悪くない証拠と思ってしまう
調子が悪いと休むことがままならない
夏場も過ぎて、だいぶ落ち着き、読書でも始めるかと思ったときに、手に取ったのが心の病がらみの本2冊、さらに落ち着いてきた冬、思い出しながら感想を
最相葉月のセラピスト、日本の心理学の巨人、河合隼雄が日本に広めた心理療法の一種、箱庭療法の話から入り、セラピスト、今の心理療法士と言う職業の歴史について淡々と語っている。彼女の文章は丁寧で誠実で、読んでいて落ち着く
そして、衝撃のカミングアウト、でも彼女はあまり騒ぎ立てない
最後、人間とは?、社会のなかの人間とは?と言う根源的なテーマに向かい、色々あっていいんだよという優しい雰囲気で本は終わる
うん、人間、コミュニケーションが大事だなと納得。
私も小さい頃、コミュニケーションが苦手で、そのまま人と関わらない仕事に就きたいと思っていた。たまたま運良く、ひとり気ままでワガママを押し通せる職に就いてしまった。この若い時に苦労しなかったことのしっぺ返しがこの歳でブーメランのように自分に帰ってきたと思っている
もう一冊は、山本文緒の「再婚生活 私のうつ闘病日記」
こちら、うつを患った著者の痛い話
さすが直木賞作家、痛いを描かせるとうまい。うつを患っている著者はこれでもかと大袈裟に騒ぎ立てる。これは演出かと疑うが、ありのままの壮絶なうつ日記らしい。あとがきの書き手は別人かと思うほど落ち着き払っており、治るってこういうことかと納得。そして、さすが作家、その言葉に勇気をもらう
今年もあと少し、世間も私もあまり良くなかった年だったかもしれないが
良い悪いは別にして、こんな年もある
まるで論語の世界に入りつつある
ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ
2020年11月28日 日常
日本、韓国、中国、台湾と、東アジアの国々から、才能のある新しい映画監督さんが次々と出てくるのは嬉しい
これは中国の新しい世代の監督さんの二作目
後半と前半でテンポが全然違う
前半は、生まれ故郷に戻った主人公が色んな人を訪ねて、彼の身の上をのらりくらりと映してくれる。ここのテンポが緩やかで、話が全然見えないことと相して、眠い眠い
ところが後半のあるシーンからは、最後までワンカットで撮られていて、なんともめまぐるしく新鮮。瞬き1つ許されず、話の展開について行こうと必死になります
トンネルを抜けると別の世界に通じている、主人公が寡黙など、村上春樹的世界を思わせる。村上的世界の始まりがどこにあるのか知らないけど、ポストモダンのアジアでは、メタファーと喪失に満ちた世界観が共有されていることを感じる
これは中国の新しい世代の監督さんの二作目
後半と前半でテンポが全然違う
前半は、生まれ故郷に戻った主人公が色んな人を訪ねて、彼の身の上をのらりくらりと映してくれる。ここのテンポが緩やかで、話が全然見えないことと相して、眠い眠い
ところが後半のあるシーンからは、最後までワンカットで撮られていて、なんともめまぐるしく新鮮。瞬き1つ許されず、話の展開について行こうと必死になります
トンネルを抜けると別の世界に通じている、主人公が寡黙など、村上春樹的世界を思わせる。村上的世界の始まりがどこにあるのか知らないけど、ポストモダンのアジアでは、メタファーと喪失に満ちた世界観が共有されていることを感じる
テリー・ギリアムのドンキ・ホーテ
2020年11月20日 日常 コメント (2)
主人公が監督を務めるCM撮影現場から始まり
自主映画の撮影に没頭していた主人公の学生時代へ飛んで
その昔の映画に出演していたドンキ・ホーテ役の老人に再会するところから、旅は狂気の道へまっしぐら
ここからは白昼夢の連続で
警察に追われたり、不法移民の村へ迷い込んだり、豪奢な城で行われる劇中劇が出てきたり、エンターテーメントとして成立している?それとも破綻してる?というぎりぎりの線上で、テンポよく話が進む。旅は続くよ、いつまでも
ワクワクしながらも、騒がしく、そして落ち着かないテリー・ギリアムの世界がたっぷりと楽しめる2時間。逆に言えば、テリー・ギリアムを知らなければ、ちょっと退屈かも
スターウォーズを見てない僕にとって主演のアダム・ドライバーはジム・ジャームッシュ作品の人なんだけど、ポスト・ジョニー・デップに納得。デッド・マンのジョニー・デップはカッコ良かった
この作品でも、最初、主演はジョニー・デップだったけど、紆余曲折があってアダム・ドライバーになったらしい
自主映画の撮影に没頭していた主人公の学生時代へ飛んで
その昔の映画に出演していたドンキ・ホーテ役の老人に再会するところから、旅は狂気の道へまっしぐら
ここからは白昼夢の連続で
警察に追われたり、不法移民の村へ迷い込んだり、豪奢な城で行われる劇中劇が出てきたり、エンターテーメントとして成立している?それとも破綻してる?というぎりぎりの線上で、テンポよく話が進む。旅は続くよ、いつまでも
ワクワクしながらも、騒がしく、そして落ち着かないテリー・ギリアムの世界がたっぷりと楽しめる2時間。逆に言えば、テリー・ギリアムを知らなければ、ちょっと退屈かも
スターウォーズを見てない僕にとって主演のアダム・ドライバーはジム・ジャームッシュ作品の人なんだけど、ポスト・ジョニー・デップに納得。デッド・マンのジョニー・デップはカッコ良かった
この作品でも、最初、主演はジョニー・デップだったけど、紆余曲折があってアダム・ドライバーになったらしい
やっと読みました。美藤さんの日記で知ってから、楽しみに取っていた本
爽やかな秋晴れのもと読了
長編小説を読破した充実感に満たされ、
中学生の時に、パール・バックの「大地」を読破したときの新鮮さを思い出す
物語を読むって、いくつになっても楽しい
前半の半島での話、風土と文化と人がしっかりと描写されていて、主人公たちに心を掴まれる、
各章のあたまにいつの出来事かわかるように、何年何月と書かれていて、前半は丁寧に時間が進んでいることがわかり、サクサクとページを消化しながら、物語にハマってゆく
後半、徐々に明らかにされるパチンコのメタファーもガッテンしまくり
ただ、下巻の半ばあたりから、描かれる月日の間隔が不定期になり、章の長さが短くなったり長くなったり、月日のスピードの加速減速が繰り返され、その度についてゆけず、ページを戻って確認したりと、物語をじっくりと味わう余裕が少しなくなる
歳のせいで、物語を読むのに必要な記憶が衰えたからかと訝しってしまったり
また、ハッテン場、エイズといった時代特有のアイテムや、善き人が出てくるドラマチックな展開は、少し安易すぎなかとツッコミを入れたくもなる
それでも良いもの読んだと思わせてくれる
世の中、しょうがないことがいっぱいだけど、人はまだまだ捨てたもんじゃない
美藤さん、良い本を教えてくれてありがとう
爽やかな秋晴れのもと読了
長編小説を読破した充実感に満たされ、
中学生の時に、パール・バックの「大地」を読破したときの新鮮さを思い出す
物語を読むって、いくつになっても楽しい
前半の半島での話、風土と文化と人がしっかりと描写されていて、主人公たちに心を掴まれる、
各章のあたまにいつの出来事かわかるように、何年何月と書かれていて、前半は丁寧に時間が進んでいることがわかり、サクサクとページを消化しながら、物語にハマってゆく
後半、徐々に明らかにされるパチンコのメタファーもガッテンしまくり
ただ、下巻の半ばあたりから、描かれる月日の間隔が不定期になり、章の長さが短くなったり長くなったり、月日のスピードの加速減速が繰り返され、その度についてゆけず、ページを戻って確認したりと、物語をじっくりと味わう余裕が少しなくなる
歳のせいで、物語を読むのに必要な記憶が衰えたからかと訝しってしまったり
また、ハッテン場、エイズといった時代特有のアイテムや、善き人が出てくるドラマチックな展開は、少し安易すぎなかとツッコミを入れたくもなる
それでも良いもの読んだと思わせてくれる
世の中、しょうがないことがいっぱいだけど、人はまだまだ捨てたもんじゃない
美藤さん、良い本を教えてくれてありがとう
イタリアといえばマンマ抜きには語れないけど、
これは主人公の男性と、彼の父と、幼なじみの男友達のお話、三人とも山が好き
イタリアといえば陽気な人たちと思っていたのに
北部ミラノ出身のせいか、主役の男性たちは口数も少なく頑固さが目立つ
山男が寡黙なのは世界共通!?
時代、育ちの違いからか山への関わり方は三者三様、それぞれ違うアプローチで山に関わる。アプローチする道は異なるため、お互い疎遠になったり、ひょんなことからお互いの道が交錯したりと話は進む
しかし、道がどんなところを通ろうとも、道の上にある山はいつも存在している、例え曇ってそれが見えなくても、あまりにも険しく登れなくても
もちろん母も出てきて、対称的にとっても社交的、山は女性のメタファーかと思ったけど、そういう訳でもない
私はこの小説を読み、不器用で頑固な自分に気づく、気づいても変われないのが残念なんだけどね
これは主人公の男性と、彼の父と、幼なじみの男友達のお話、三人とも山が好き
イタリアといえば陽気な人たちと思っていたのに
北部ミラノ出身のせいか、主役の男性たちは口数も少なく頑固さが目立つ
山男が寡黙なのは世界共通!?
時代、育ちの違いからか山への関わり方は三者三様、それぞれ違うアプローチで山に関わる。アプローチする道は異なるため、お互い疎遠になったり、ひょんなことからお互いの道が交錯したりと話は進む
しかし、道がどんなところを通ろうとも、道の上にある山はいつも存在している、例え曇ってそれが見えなくても、あまりにも険しく登れなくても
もちろん母も出てきて、対称的にとっても社交的、山は女性のメタファーかと思ったけど、そういう訳でもない
私はこの小説を読み、不器用で頑固な自分に気づく、気づいても変われないのが残念なんだけどね
南欧の国々は明るく陽気だと言われるが、彼らだって悩みはあるし、影だってある
スペインもポルトガルもギリシャも1970年代まで独裁国家だったし、
スペインは国内の多様な文化であるバスクやカタルーニャを認めなかったし、
ポルトガルはアフリカの植民地を手放さなかったし、
ギリシャは隣国キプロスへ侵攻した
そんな南欧のポルトガルの影の雰囲気に満ちたお話
人間の負の部分が語られ、嫌な気分になりながら、挫折しそうになりながら、最後まで付き合うと、なぜか愛着まで湧いてきて、あら不思議
生きとし生けるもの、悩みがあり、影が無い方がおかしい
スペインもポルトガルもギリシャも1970年代まで独裁国家だったし、
スペインは国内の多様な文化であるバスクやカタルーニャを認めなかったし、
ポルトガルはアフリカの植民地を手放さなかったし、
ギリシャは隣国キプロスへ侵攻した
そんな南欧のポルトガルの影の雰囲気に満ちたお話
人間の負の部分が語られ、嫌な気分になりながら、挫折しそうになりながら、最後まで付き合うと、なぜか愛着まで湧いてきて、あら不思議
生きとし生けるもの、悩みがあり、影が無い方がおかしい