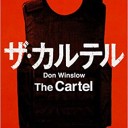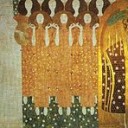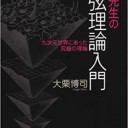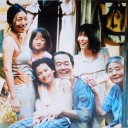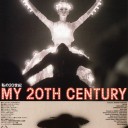スマホに変えて良かったことは、ミュージックプレーヤーとキンドルと携帯がオールインワンになったことに加え、デジカメが手に入ったこと
と言うことで、美藤さんに倣って、気になった植物や虫を撮っている
美藤さんの日記でコミカンソウのことを読んで以来、家の周りのコミカンソウもどきが気になってしょうがなかった。
上の写真が私の知っているコミカンソウ、大腸内視鏡検査をした病院の玄関脇に生えていたのをパシャり
下の写真は隣の家との境に生えているコミカンソウもどき。ググってみるとすぐに見つかる、ナガエコミカンソウと言う帰化植物らしい
こちらの葉っぱも、互生なのに、マメ科の羽状複葉と見間違える
と投稿したものの、写真の順番が…
システムを使いこなすのは難しい
下がコミカンソウ、上がナガエコミカンソウ
と言うことで、美藤さんに倣って、気になった植物や虫を撮っている
美藤さんの日記でコミカンソウのことを読んで以来、家の周りのコミカンソウもどきが気になってしょうがなかった。
上の写真が私の知っているコミカンソウ、大腸内視鏡検査をした病院の玄関脇に生えていたのをパシャり
下の写真は隣の家との境に生えているコミカンソウもどき。ググってみるとすぐに見つかる、ナガエコミカンソウと言う帰化植物らしい
こちらの葉っぱも、互生なのに、マメ科の羽状複葉と見間違える
と投稿したものの、写真の順番が…
システムを使いこなすのは難しい
下がコミカンソウ、上がナガエコミカンソウ
5年前に取った大腸の悪性腫瘍性ポリープの経過観察のため、大腸内視鏡を入れる
前回は、痛くて痛くてしょうがなかったのに、同じ先生なのに、今回は無痛!
あまりにも快適で、モニターに映し出された自分の白モツを眺めながら、このあと何を食べようかと思案する
健康診断もそうだけど、検査の後の空腹に何を入れようかと考えるのは楽しい
前日の夜から何も食べてないので、24時間弱のプチプチ絶食明け
ちなみに今回は、会計が終わったあと、病院の飲食スペースで、用意していた選りすぐりの高級バナナを一本食べる、美味い!
バナナで落ち着いたあと何を食べるか?、白モツを見ながら出した答えはかりんとう。買い置きしていた正統派の黒糖かりんとうが家のお菓子棚にあるのを思い出す。黒くて太くて堅いやつを齧る、美味い!
前回は、痛くて痛くてしょうがなかったのに、同じ先生なのに、今回は無痛!
あまりにも快適で、モニターに映し出された自分の白モツを眺めながら、このあと何を食べようかと思案する
健康診断もそうだけど、検査の後の空腹に何を入れようかと考えるのは楽しい
前日の夜から何も食べてないので、24時間弱のプチプチ絶食明け
ちなみに今回は、会計が終わったあと、病院の飲食スペースで、用意していた選りすぐりの高級バナナを一本食べる、美味い!
バナナで落ち着いたあと何を食べるか?、白モツを見ながら出した答えはかりんとう。買い置きしていた正統派の黒糖かりんとうが家のお菓子棚にあるのを思い出す。黒くて太くて堅いやつを齧る、美味い!
使っているガラケの液晶が死にかかって、7年ぶりのスマホに戻る
前回のスマホは小さい画面でネットを使いこなすことができず、携帯電話として使うには重すぎ、半年ほどで手放した
この7年で技術は進歩するもので、老眼にも見えやすく、さらにフリーのWi-Fi環境もいろいろあって、それなりにスマホを便利に使っている
何と言っても、音楽プレーヤーとキンドルと携帯がオールインになったのが素晴らしい
ただ、家族との連絡に使っているLINEはまだまだ使いこなせてなく、「書いたよ」、「読んでないよ」でもめることも。さらに職場の若手とLINE・IDの交換をするも、一度も連絡には使ってなく、従来通りメールでやりとりしている
前回のスマホは小さい画面でネットを使いこなすことができず、携帯電話として使うには重すぎ、半年ほどで手放した
この7年で技術は進歩するもので、老眼にも見えやすく、さらにフリーのWi-Fi環境もいろいろあって、それなりにスマホを便利に使っている
何と言っても、音楽プレーヤーとキンドルと携帯がオールインになったのが素晴らしい
ただ、家族との連絡に使っているLINEはまだまだ使いこなせてなく、「書いたよ」、「読んでないよ」でもめることも。さらに職場の若手とLINE・IDの交換をするも、一度も連絡には使ってなく、従来通りメールでやりとりしている
色々な都合で中断していたジム通いを、体が少し重くなって、さらに肩こりがどうしようもなくなったので、4年ぶりに再開することに
そして昨日、いま流行りのHIITを取り入れたフィットネスのクラスへ参加する
音楽に合わせて筋トレを休みなく続けるプログラムで、むかし流行ったビリーズブートキャンプの鬼軍曹が優しい女性のインストラクターに代わったようなもの
怠けていて当分使ってなかった身体中の筋肉を総動員、最後はへばって、もう足が上がらないという時に、インスクターが笑顔でもう一回と励ましてくれる
汗と筋肉痛が気持ちいい〜!
ストイックな性格ではないので、辛い運動を1人でするのは絶対無理
エアコンの効いた快適なフィットネスジムで、優しいインストラクターと仲間がいるからできるんだよなと納得
かつて通ってた頃に見かけた顔がちらほら
きっと彼らはこの4年間もジム通いを続けてきたんだろうけど、中にはちょっとメタボ体型の方もいる
このプログラムを続けても痩せる保証はないんだとも納得
そして昨日、いま流行りのHIITを取り入れたフィットネスのクラスへ参加する
音楽に合わせて筋トレを休みなく続けるプログラムで、むかし流行ったビリーズブートキャンプの鬼軍曹が優しい女性のインストラクターに代わったようなもの
怠けていて当分使ってなかった身体中の筋肉を総動員、最後はへばって、もう足が上がらないという時に、インスクターが笑顔でもう一回と励ましてくれる
汗と筋肉痛が気持ちいい〜!
ストイックな性格ではないので、辛い運動を1人でするのは絶対無理
エアコンの効いた快適なフィットネスジムで、優しいインストラクターと仲間がいるからできるんだよなと納得
かつて通ってた頃に見かけた顔がちらほら
きっと彼らはこの4年間もジム通いを続けてきたんだろうけど、中にはちょっとメタボ体型の方もいる
このプログラムを続けても痩せる保証はないんだとも納得
いやいや、このふた月は長かった
6月終わりから仕事が詰まっていて、当初二週間を予定していた帰省も一週間弱で切り上げて仕事に追われる。先週末で大きな仕事の山もほぼ峠を越して、ほっと一息
何が辛かったかって、趣味の夏山、今年はどこにも行けず仕舞いだったこと
そんな仕事に明け暮れた今年の夏のストレス解消は、ウィズロウの「麻薬との戦争」
犬の力とザ・カルテル、どちらも上下巻で、総ページ数2000ページ弱を一ヶ月弱かけて読む
帰省、仕事とも移動が多く、このひと月の半分近くは車を運転していたか、船に乗っていたような。というわけで、その半分は本が読めなかったので、2000ページを実質15日ほどで
特に最後の300ページほどは止まらず、ぐいぐい引っ張られる
そして、先ほど無事読了!
すっかり打ちのめされました。圧倒的な暴力の世界、それもかなりリアルな北中米をめぐる悪の世界。打ちのめされながらも読めたのは、暴力の溢れる世界でありながらも、わずかながらも未来があるのではという希望にすがったため
いやいや、ウィズロウさん、ちらりと希望を持たさせるのうまいんだな
心折れそうになると、頃合いを図ったかのように、家族の話が展開されて、希望に救われる
まあ、どんなにひどい世界でも希望はあることはあるんだろうけど、悪に簡単に踏み潰されそうなほど脆い希望で、それが続編、ザ・ボーダーで未来につながっているのか、ちょっとワクワク
でも、時代はメキシコとアメリカの国境に壁を作ろうとするトランプさんなんだよね、希望はあるのか!?
でも、続編を読み始めるまで、しばし休憩、遅れた夏休みです
6月終わりから仕事が詰まっていて、当初二週間を予定していた帰省も一週間弱で切り上げて仕事に追われる。先週末で大きな仕事の山もほぼ峠を越して、ほっと一息
何が辛かったかって、趣味の夏山、今年はどこにも行けず仕舞いだったこと
そんな仕事に明け暮れた今年の夏のストレス解消は、ウィズロウの「麻薬との戦争」
犬の力とザ・カルテル、どちらも上下巻で、総ページ数2000ページ弱を一ヶ月弱かけて読む
帰省、仕事とも移動が多く、このひと月の半分近くは車を運転していたか、船に乗っていたような。というわけで、その半分は本が読めなかったので、2000ページを実質15日ほどで
特に最後の300ページほどは止まらず、ぐいぐい引っ張られる
そして、先ほど無事読了!
すっかり打ちのめされました。圧倒的な暴力の世界、それもかなりリアルな北中米をめぐる悪の世界。打ちのめされながらも読めたのは、暴力の溢れる世界でありながらも、わずかながらも未来があるのではという希望にすがったため
いやいや、ウィズロウさん、ちらりと希望を持たさせるのうまいんだな
心折れそうになると、頃合いを図ったかのように、家族の話が展開されて、希望に救われる
まあ、どんなにひどい世界でも希望はあることはあるんだろうけど、悪に簡単に踏み潰されそうなほど脆い希望で、それが続編、ザ・ボーダーで未来につながっているのか、ちょっとワクワク
でも、時代はメキシコとアメリカの国境に壁を作ろうとするトランプさんなんだよね、希望はあるのか!?
でも、続編を読み始めるまで、しばし休憩、遅れた夏休みです
今年は日本・オーストリア外交樹立150周年らしい。ということで、オーストリア関連の大きな展覧会が2つ企画されている、上野のクリムト展と六本木のウィーン・モダン展
この2つの展覧会を見ると、オーストリアが帝政時代から近代へ移ろうとする19世紀の芸術と工芸、およびその背景にある啓蒙主義やら世紀末思想やらを堪能できるらしい。もちろん華は世紀末ウィーンのスーパースター、クリムトとシーレ
ということで、行ってきましたクリムト展とウィーン・モダン展
大陸の大西洋岸、光のどけき田園や海岸で芸術家たちが光を捉えようとしていたとき、アルプスの北のウィーンで、しづこころなくはなのちるらむ様を捉えようとしていたウィーン分離派の生き様(アート)が楽しめる
印象派と比べると、その芸術性の評価がどうしても低くなりがちな世紀末芸術、でもそこで描かれた官能的な世界が19世紀の理想とロクでもない現実のなれの果てであり、クリムトのエロスと死の世界が近代の影をよく表徴していることが納得できることは素晴らしい
ただ、その後の結末を知っている21世紀から見れば、単なるカビ臭いハプスブルク家のお宝陳列であり、
田舎になってしまったオーストリアの負け犬の遠吠えと映らなくもない
もう少し、天才エゴン・シーレの絵を見せてくれていたら、こんな愚痴も出ないのにな〜
この2つの展覧会を見ると、オーストリアが帝政時代から近代へ移ろうとする19世紀の芸術と工芸、およびその背景にある啓蒙主義やら世紀末思想やらを堪能できるらしい。もちろん華は世紀末ウィーンのスーパースター、クリムトとシーレ
ということで、行ってきましたクリムト展とウィーン・モダン展
大陸の大西洋岸、光のどけき田園や海岸で芸術家たちが光を捉えようとしていたとき、アルプスの北のウィーンで、しづこころなくはなのちるらむ様を捉えようとしていたウィーン分離派の生き様(アート)が楽しめる
印象派と比べると、その芸術性の評価がどうしても低くなりがちな世紀末芸術、でもそこで描かれた官能的な世界が19世紀の理想とロクでもない現実のなれの果てであり、クリムトのエロスと死の世界が近代の影をよく表徴していることが納得できることは素晴らしい
ただ、その後の結末を知っている21世紀から見れば、単なるカビ臭いハプスブルク家のお宝陳列であり、
田舎になってしまったオーストリアの負け犬の遠吠えと映らなくもない
もう少し、天才エゴン・シーレの絵を見せてくれていたら、こんな愚痴も出ないのにな〜
鍼灸、足つぼ、漢方などと言った、西洋医学以外のオルタナティブな民間療法、嫌いではないです、どちらかと言えば好きかも
細かいことを言えば、これらの多くがエビデンスのない疑似科学に限りなく近く、その効用もあまり信じてはいない
さらに言えば、施術中に施術士から、気やマイナスイオンなど東洋医学のもっともらしい説明をされると、聞き流すどころか、わけないだろうとツッコミを入れたくなるぐらいだ
その怪しさというかゆるさも惹かれるところなのかも
色々と試してきた中で、今お世話になっているのは漢方と岩盤浴。一時はよくいっていたが、マイブームが終わったのは、足つぼと整体と鍼灸
自分がどのオルタナティブを受け入れているのか、その線引きも曖昧で、気持ちがよくて、害が出なくて、経済的にもお手頃なものが残ってるような
理解はできないけど、なんとなく受け入れているという点では、私にとって超弦理論と似ている
細かいことを言えば、これらの多くがエビデンスのない疑似科学に限りなく近く、その効用もあまり信じてはいない
さらに言えば、施術中に施術士から、気やマイナスイオンなど東洋医学のもっともらしい説明をされると、聞き流すどころか、わけないだろうとツッコミを入れたくなるぐらいだ
その怪しさというかゆるさも惹かれるところなのかも
色々と試してきた中で、今お世話になっているのは漢方と岩盤浴。一時はよくいっていたが、マイブームが終わったのは、足つぼと整体と鍼灸
自分がどのオルタナティブを受け入れているのか、その線引きも曖昧で、気持ちがよくて、害が出なくて、経済的にもお手頃なものが残ってるような
理解はできないけど、なんとなく受け入れているという点では、私にとって超弦理論と似ている
大栗先生の超弦理論入門 (ブルーバックス)
2019年6月13日 日常 コメント (2)
科学未来館の展示があまりにも消化不良だったのが悔しくて、そこで上映していた超弦理論(昔は超ひも理論だったけど、名前が変わったらしい)という科学映画の監修をしている大先生の本を借りてきて読む。ブルーバックスを手にするのは何十年振りだろう
この本、本が売れないこの時代に、12刷も増刷を重ねているらしい、真相はよくわかんが、科学未来館効果なのか、それともこの先生がテレビにでも出て世間で超ひも理論が熱くなってるとか!?
ウンウン、科学未来館の展示でのひも理論の理解が2%だとすると、本を読んで14%ぐらいまでには上がったかな。つまり七分の一ほどはわかったような気になった。宇宙物理学者たちの頭の中で展開されてきた理論のお話で、彼らは量子力学と重力理論の統合を目指して、抽出されたよりシンプルなモデルを作ろうとしていることを知っただけで5%ほど理解した気になれる
宇宙は10次元とか言われたら、我々が体感できる世界は超えているけど、宇宙の始まりから事象の地平線(この言葉も知らなかった!)の向こうにあるブラックホールまでを我々の地球の感覚で実感できることの方が無理で、次元についての新しい解釈が必要との話に納得
ただ、入門編で平易に説明という点で誰かにオススメできるかと言えば、手強すぎて自信はない。
この本、本が売れないこの時代に、12刷も増刷を重ねているらしい、真相はよくわかんが、科学未来館効果なのか、それともこの先生がテレビにでも出て世間で超ひも理論が熱くなってるとか!?
ウンウン、科学未来館の展示でのひも理論の理解が2%だとすると、本を読んで14%ぐらいまでには上がったかな。つまり七分の一ほどはわかったような気になった。宇宙物理学者たちの頭の中で展開されてきた理論のお話で、彼らは量子力学と重力理論の統合を目指して、抽出されたよりシンプルなモデルを作ろうとしていることを知っただけで5%ほど理解した気になれる
宇宙は10次元とか言われたら、我々が体感できる世界は超えているけど、宇宙の始まりから事象の地平線(この言葉も知らなかった!)の向こうにあるブラックホールまでを我々の地球の感覚で実感できることの方が無理で、次元についての新しい解釈が必要との話に納得
ただ、入門編で平易に説明という点で誰かにオススメできるかと言えば、手強すぎて自信はない。
なかなか上手くいかないことが多い現代社会の矛盾を上手く描いており、ベルギーのダルデンヌ兄弟の作品に近く、カンヌで受けたことに納得
テレビであふれている、楽しい娯楽性とか、評論家が並べる辛口な答が得られると思っていると、安藤サクラの涙と微笑みに打ちのめされてしまう
そう、この映画の一番の見所は
日本映画において全ての苦難を受け入れてくれる菩薩役が、平成の観音様樹木希林から令和の観音様安藤サクラにバトンタッチされたことに歴史的事実として立ち会えること
樹木希林が観音様になれたのは内田裕也というロクデモナイ旦那がいたからだけど、安藤サクラは…と思って、思い当たりました!ロクデモナイ奥田瑛二というお父さんを見て、こんなに神々しくなれたんだと
いや〜、リリー・フランキーのロクデモナさも眩しいです
テレビであふれている、楽しい娯楽性とか、評論家が並べる辛口な答が得られると思っていると、安藤サクラの涙と微笑みに打ちのめされてしまう
そう、この映画の一番の見所は
日本映画において全ての苦難を受け入れてくれる菩薩役が、平成の観音様樹木希林から令和の観音様安藤サクラにバトンタッチされたことに歴史的事実として立ち会えること
樹木希林が観音様になれたのは内田裕也というロクデモナイ旦那がいたからだけど、安藤サクラは…と思って、思い当たりました!ロクデモナイ奥田瑛二というお父さんを見て、こんなに神々しくなれたんだと
いや〜、リリー・フランキーのロクデモナさも眩しいです
チームラボに続いて、お台場のお話をもう一題
この春で中学一年生になったうちの息子、一番好きな教科はずっと体育と言っていたのに、小学生の高学年の頃から理科や算数にも興味が出てきたらしく、図書館で科学の本を借りてきてくるようになる。その延長で、一緒に科学館へも行くように。多摩地方が誇る六都科学館、泣く子も黙る天下の上野国立科学博物館、どちらも子供も大人も楽しめて、とてもお世話になった。目で見て体感できるアナログ的な技術が多く紹介されており、さらにそれらの技術の元となる、力学や波動などの共通の原理やデジタル化やフーリエ解析という共通の手法についても解説があり、アナログ、デジタルに関係なく科学技術の発展の歴史が感じられる素晴らしい展示だと、いつも感心していた。
お台場の科学未来館には、なぜか縁がなく、一度も行ってことがなかった。
そこでこの四月、卒業と入学の間、クラブ活動も行事も何もない時間ができた息子と、科学未来館デビューすることに
最新の科学技術について科学コミュニケーションによりわかりやすく展示とあり、期待に胸おどる。確かに選ばれているテーマは最新である。ただ、最新の科学技術は個別の専門性があまりにも進んでいて理解するのは難しい。そんな難しいテーマが専門家監修のもと展示されているが、関連のない様々なテーマがずらりと並んでおり、次々と現れる難しい解説に打ち負かされる。監修した科学者は隣のテーマの展示内容を理解できるのかと疑いたくなるほどだ
あまりにも難しく、なぜなぜと疑問を感じさせるかなり手前で好奇心は途切れ、ふ〜んと感心するばかり、結果として「科学ってすごいね」という広く浅くそして軽い印象が残る
窓からフジテレビの本社がよく見え、社会的使命ではなくテレビの面白さの可能性を追求しようとしていた軽いフジテレビが近くにあるのは類は類を呼んだ結果かと、あまりもの分からなさの苛立ちから、皮肉りたくもなる
会場には多くの科学コミュニケーターがいて、気軽に声を掛けてくれて、展示の理解を助けてくれる。対応は丁寧なのだが、「私もよく理解できてないんですよね、でも理解できなくてもなんとなく感じてもらって好奇心を持ってもらえればれば、我々も嬉しい」と現代アートの鑑賞法のような話でお茶を濁される
順番としては、科学未来館で科学への興味を持って、さらに知りたければ科博へ行くというのが正しいかと。順序を間違えてしまったようで、残念だった
この春で中学一年生になったうちの息子、一番好きな教科はずっと体育と言っていたのに、小学生の高学年の頃から理科や算数にも興味が出てきたらしく、図書館で科学の本を借りてきてくるようになる。その延長で、一緒に科学館へも行くように。多摩地方が誇る六都科学館、泣く子も黙る天下の上野国立科学博物館、どちらも子供も大人も楽しめて、とてもお世話になった。目で見て体感できるアナログ的な技術が多く紹介されており、さらにそれらの技術の元となる、力学や波動などの共通の原理やデジタル化やフーリエ解析という共通の手法についても解説があり、アナログ、デジタルに関係なく科学技術の発展の歴史が感じられる素晴らしい展示だと、いつも感心していた。
お台場の科学未来館には、なぜか縁がなく、一度も行ってことがなかった。
そこでこの四月、卒業と入学の間、クラブ活動も行事も何もない時間ができた息子と、科学未来館デビューすることに
最新の科学技術について科学コミュニケーションによりわかりやすく展示とあり、期待に胸おどる。確かに選ばれているテーマは最新である。ただ、最新の科学技術は個別の専門性があまりにも進んでいて理解するのは難しい。そんな難しいテーマが専門家監修のもと展示されているが、関連のない様々なテーマがずらりと並んでおり、次々と現れる難しい解説に打ち負かされる。監修した科学者は隣のテーマの展示内容を理解できるのかと疑いたくなるほどだ
あまりにも難しく、なぜなぜと疑問を感じさせるかなり手前で好奇心は途切れ、ふ〜んと感心するばかり、結果として「科学ってすごいね」という広く浅くそして軽い印象が残る
窓からフジテレビの本社がよく見え、社会的使命ではなくテレビの面白さの可能性を追求しようとしていた軽いフジテレビが近くにあるのは類は類を呼んだ結果かと、あまりもの分からなさの苛立ちから、皮肉りたくもなる
会場には多くの科学コミュニケーターがいて、気軽に声を掛けてくれて、展示の理解を助けてくれる。対応は丁寧なのだが、「私もよく理解できてないんですよね、でも理解できなくてもなんとなく感じてもらって好奇心を持ってもらえればれば、我々も嬉しい」と現代アートの鑑賞法のような話でお茶を濁される
順番としては、科学未来館で科学への興味を持って、さらに知りたければ科博へ行くというのが正しいかと。順序を間違えてしまったようで、残念だった
イザベル・アジェンデの新作を楽しむ
彼女にかかると日本男子も情熱的になれるのねと感心
ポーランド出身のユダヤ系ポーランド人の主人公も、きっとユダヤ系ポーランド人から見たら、違うよと違和感を感じてるのだと思う
でも、小説はフィクションなんだから、そんなの関係ないとばかりに、物語にのめりこませてくれる彼女の語りのうまさに惚れる
ポール・オースターの新作同様、こちらも長い作品じゃないんだけど、紡がれる時間が描かれていて、読後の余韻も含めて、口に残ったチョコレートの香りのように永く楽しめる
彼女にかかると日本男子も情熱的になれるのねと感心
ポーランド出身のユダヤ系ポーランド人の主人公も、きっとユダヤ系ポーランド人から見たら、違うよと違和感を感じてるのだと思う
でも、小説はフィクションなんだから、そんなの関係ないとばかりに、物語にのめりこませてくれる彼女の語りのうまさに惚れる
ポール・オースターの新作同様、こちらも長い作品じゃないんだけど、紡がれる時間が描かれていて、読後の余韻も含めて、口に残ったチョコレートの香りのように永く楽しめる
我らがポールオースターの新刊
日本では昨年の秋に出版、原作は2009年なので10年遅れなのね
油断して読み始めたら、いつの間にか創作を読む快感にどっぷりと浸かっていて、出口なんてないのはわかっているんだけど、どんどん彼の作ったフィクションの入れ子構造の世界へ入ってゆく
あ〜、もう終わっちゃうのねと、最後惜しみつつ最後の1ページを読み終えるまで快感は続く
ちなみに話は陳腐だなと思えたんだけど、そんな陳腐な話でもこんなに面白いと思わせるように書く作家の力って素晴らしい。これ素直に褒めてるんです!
日本では昨年の秋に出版、原作は2009年なので10年遅れなのね
油断して読み始めたら、いつの間にか創作を読む快感にどっぷりと浸かっていて、出口なんてないのはわかっているんだけど、どんどん彼の作ったフィクションの入れ子構造の世界へ入ってゆく
あ〜、もう終わっちゃうのねと、最後惜しみつつ最後の1ページを読み終えるまで快感は続く
ちなみに話は陳腐だなと思えたんだけど、そんな陳腐な話でもこんなに面白いと思わせるように書く作家の力って素晴らしい。これ素直に褒めてるんです!
もうひと月以上も前のお話、寒い冬の日
お台場のプロジェクトマッピング、チームラボにゆく
外国からの観光客が半分以上、寒い屋外で、皆おとなしく並んで、おそらく理解できていないであろう日本語の説明を聞きながらおとなしく待っている
お、外国の人たちもちゃんと列に並んで待てるんだと感心、郷に入れば郷に従えか!?
中ももちろん激混み、プロジェクトマッピングを見に行ったはずなのに、プロジェクトマッピングを見ている人を見に行ったようなもので、ちょっとストレスが溜まる
全体に、アジアの浄土をイメージした雰囲気なんだけど、無国籍な世界が広がっていて、欧米人にはアジア的なものを味わえるテーマパークとして、アジア人には懐かしいんだけど見たことのない新鮮な世界が楽しめて、日本人と世界中からの観光客で埋まっているのに納得。
裏を返せば、観光客は、外に本物のアジアがあるのに、どうして長時間並んでまで、高いお金を払ってまで、わざわざ混んでいる空間の中で、人工的な偽物のアジアを見るのか?
知らない土地で、里や海や山へ行って、神社仏閣を見たり、神聖な霊場を巡ったりって、時間的にも手段的にもなかなか大変で、東京で半日で廻れて、お手軽で安全なのが一番ということか
終了間際、人の少なくなった空間だとイメージが全然違う、それこそ見たこともない浄土感が味わえ、よくできていると感心する
でも、所詮プロジェクトマッピング、偽物で安物っぽい臭いもぷんぷんする
お台場のプロジェクトマッピング、チームラボにゆく
外国からの観光客が半分以上、寒い屋外で、皆おとなしく並んで、おそらく理解できていないであろう日本語の説明を聞きながらおとなしく待っている
お、外国の人たちもちゃんと列に並んで待てるんだと感心、郷に入れば郷に従えか!?
中ももちろん激混み、プロジェクトマッピングを見に行ったはずなのに、プロジェクトマッピングを見ている人を見に行ったようなもので、ちょっとストレスが溜まる
全体に、アジアの浄土をイメージした雰囲気なんだけど、無国籍な世界が広がっていて、欧米人にはアジア的なものを味わえるテーマパークとして、アジア人には懐かしいんだけど見たことのない新鮮な世界が楽しめて、日本人と世界中からの観光客で埋まっているのに納得。
裏を返せば、観光客は、外に本物のアジアがあるのに、どうして長時間並んでまで、高いお金を払ってまで、わざわざ混んでいる空間の中で、人工的な偽物のアジアを見るのか?
知らない土地で、里や海や山へ行って、神社仏閣を見たり、神聖な霊場を巡ったりって、時間的にも手段的にもなかなか大変で、東京で半日で廻れて、お手軽で安全なのが一番ということか
終了間際、人の少なくなった空間だとイメージが全然違う、それこそ見たこともない浄土感が味わえ、よくできていると感心する
でも、所詮プロジェクトマッピング、偽物で安物っぽい臭いもぷんぷんする
光と影の寓話
このところ好きな映画を観る余裕がなかったので、妻子が実家に帰っている独身の春休み、吉祥寺のアップリンクで映画を楽しむ
20年前のハンガリー映画のリストア版、観終わってから以前に観ていたことを何となく思い出す
20世紀は電気の新しい時代、でも、アンシャン・レジームの名残もいたるところに、その混在が美しい。もちろん、前者が光で、後者が影
ここから余談へ
映画は、男性の飾りであった女性が自立すること、いわゆるフェミニズム運動も含まれていて、途中、男性の学者が「女性は感情的で下等であり、人の話を聞くことができない、云々」と、女性をこき下ろす演説が結構続くシーンがある。観ていた初老のご婦人二人が「この人の考え方ちょっと変わってるわね」と、思わず話し始めてしまう。それでスウィッチが入ったのか、彼女たちの会話は映画の最後まで断続的に続き、終映後、近くにいたおじさんに「映画館では喋ってはダメなんです、せっかくの映画が台無しだった」と説教されていた。
ウンウン、この映画の監督さんは女性で、あのシーンは今も変わらぬ男性への嫌味だったと思うんだけど、ストレートに初老のおばさんの心を打ちのめしてしまったことにちょっと驚き。この映画が、さらに公開から20年後に再上映された企画の意図にあるのかどうかわからないが、この閉塞感に満ちた今の時代に寛容さの必要性を訴えっていると思ったのに…。あのおじさんの態度は不寛容と断定していいのかと
映画館のなかで、色々と考えさせられた貴重な体験をした
やっぱり映画を映画館で観るのは楽しい
このところ好きな映画を観る余裕がなかったので、妻子が実家に帰っている独身の春休み、吉祥寺のアップリンクで映画を楽しむ
20年前のハンガリー映画のリストア版、観終わってから以前に観ていたことを何となく思い出す
20世紀は電気の新しい時代、でも、アンシャン・レジームの名残もいたるところに、その混在が美しい。もちろん、前者が光で、後者が影
ここから余談へ
映画は、男性の飾りであった女性が自立すること、いわゆるフェミニズム運動も含まれていて、途中、男性の学者が「女性は感情的で下等であり、人の話を聞くことができない、云々」と、女性をこき下ろす演説が結構続くシーンがある。観ていた初老のご婦人二人が「この人の考え方ちょっと変わってるわね」と、思わず話し始めてしまう。それでスウィッチが入ったのか、彼女たちの会話は映画の最後まで断続的に続き、終映後、近くにいたおじさんに「映画館では喋ってはダメなんです、せっかくの映画が台無しだった」と説教されていた。
ウンウン、この映画の監督さんは女性で、あのシーンは今も変わらぬ男性への嫌味だったと思うんだけど、ストレートに初老のおばさんの心を打ちのめしてしまったことにちょっと驚き。この映画が、さらに公開から20年後に再上映された企画の意図にあるのかどうかわからないが、この閉塞感に満ちた今の時代に寛容さの必要性を訴えっていると思ったのに…。あのおじさんの態度は不寛容と断定していいのかと
映画館のなかで、色々と考えさせられた貴重な体験をした
やっぱり映画を映画館で観るのは楽しい
角田光代に続いて、売れているけど今まで縁がなかった作家第二弾として、東山彰良を選ぶ
両親も本人も台湾人だけど、日本で育った直木賞作家
描かれている時代が大好きな牯嶺街少年殺人事件や恋恋風塵と同じということで、迷わず「流」を選ぶ
ちなみに東山はエドワード・ヤン監督や侯孝賢監督の1世代下で、若い世代から見たあの昏迷の台湾にも興味があって
三世代に渡る一族のお話なんだけど、「百年の孤独」や「愉楽」で感じられた時代のうねりはなく、あくまでもスピード感重視のハードボイルド青春小説、角田光代的地雷原もなく、ストレス解消によろしい
次は「僕が殺した人と僕を殺した人」かな
両親も本人も台湾人だけど、日本で育った直木賞作家
描かれている時代が大好きな牯嶺街少年殺人事件や恋恋風塵と同じということで、迷わず「流」を選ぶ
ちなみに東山はエドワード・ヤン監督や侯孝賢監督の1世代下で、若い世代から見たあの昏迷の台湾にも興味があって
三世代に渡る一族のお話なんだけど、「百年の孤独」や「愉楽」で感じられた時代のうねりはなく、あくまでもスピード感重視のハードボイルド青春小説、角田光代的地雷原もなく、ストレス解消によろしい
次は「僕が殺した人と僕を殺した人」かな
角田光代訳源氏物語が中巻まで出ているのに気づく
角田光代のエッセイにはそんじゅそこらで出会うからか、彼女の小説も読んだつもりになってたが、真面目に読んだことがないのに気づく。
初角田光代が源氏物語というのもハードルが高そうなので、軽めのものを一冊と思って選んだのコレ
う〜ん、全然軽くないです、重い、読んでびっくり
下品な言い方だけど、初めて裏ビデオを見たような衝撃、いやいやそういう世界があるのは知ってたけど、自分の中にも嫉妬とか見栄などがあるのは認めるけど
お受験のドロドロした部分だけ濃縮して見ると、ちょっと引いてしまった
しかし、引くほどドロドロしたものをそれらしく描ける彼女の才能に感嘆もし、
角田光代訳源氏物語、さぞやドロドロものかと期待してるが、Amazonのレビューを見る限り、読みやすくて、さっぱりしているらしい
角田光代のエッセイにはそんじゅそこらで出会うからか、彼女の小説も読んだつもりになってたが、真面目に読んだことがないのに気づく。
初角田光代が源氏物語というのもハードルが高そうなので、軽めのものを一冊と思って選んだのコレ
う〜ん、全然軽くないです、重い、読んでびっくり
下品な言い方だけど、初めて裏ビデオを見たような衝撃、いやいやそういう世界があるのは知ってたけど、自分の中にも嫉妬とか見栄などがあるのは認めるけど
お受験のドロドロした部分だけ濃縮して見ると、ちょっと引いてしまった
しかし、引くほどドロドロしたものをそれらしく描ける彼女の才能に感嘆もし、
角田光代訳源氏物語、さぞやドロドロものかと期待してるが、Amazonのレビューを見る限り、読みやすくて、さっぱりしているらしい
春のせいか、花粉のせいか、何が原因かわからないけど、体調が悪く、この日記を書くまでなかなかたどり着けない日々
年頃もあるんだろうなと
今朝、憂鬱で折れそうになったのに、ブラームスのシンフォニーを電車で聴いていると、不思議と気持ちが晴れた。体のたるいのは変わらないんだけどね
日記も少しずつ、コメントも少しずつ書こうと思う
年頃もあるんだろうなと
今朝、憂鬱で折れそうになったのに、ブラームスのシンフォニーを電車で聴いていると、不思議と気持ちが晴れた。体のたるいのは変わらないんだけどね
日記も少しずつ、コメントも少しずつ書こうと思う
昨年の12月、吉祥寺にアップリンクができていたのを知る
正月何か映画でも見ようとアップリンクのHPを見てたら、バーナーに吉祥寺とあるのに気づいて、ポチッと。あ〜、なんと吉祥寺駅前のパルコの地下二階、本屋さんだったところに、それもスクリーンが5つも、素敵!
開館記念は見逃した映画特集。見たか見逃したか記憶がうろ覚えで、ずっと気になっていた幻の作品、牯嶺街少年殺人事件が掛かっているのを発見。正月3日までの上映で、行ける日は最終日の3日しかなく、夕方の6時開演で終わるのは10時と少し遅いのが気になったが、これは行くしかないと、意を決して吉祥寺へ
素晴らしく、打ちのめされた。映画に必要な要素がすべて込められており、映像を使った表現芸術の一つの完成形である。
4時間ずっと映画に惹きつけらたままで、どのシーンも見逃すまいと、食い入るように見ていたため、疲れたけど、満足。最後、坂道を転がり落ちるように絶望的な結末に突き進むところで、少しベティー。ブルーを思い出す。そういえば、どちらも1990年前後の同じ頃に撮られたんだよね。光と影のモザイク社会で、人生は不条理との葛藤であるという近代的不安を見事に描き切っている。打ちのめされました。
ちなみに、この映画観てました。いつ、どこでだったかはとんと思い出せないんだけど、最初と最後の合格者名の読み上げがラジオから流れてくるシーン、尋問室に冷房用の氷が置かれているシーンなど、デジャブを感じる。もしかしたら他の映画の似たようなシーンと勘違いしてるのだけかもしれないけど、きっと若い頃見てます。当時はこの映画の良さがまだわからず、途中寝落ちしてしまい、内容を覚えてなく、観た記憶がないのかもしれない。
正月何か映画でも見ようとアップリンクのHPを見てたら、バーナーに吉祥寺とあるのに気づいて、ポチッと。あ〜、なんと吉祥寺駅前のパルコの地下二階、本屋さんだったところに、それもスクリーンが5つも、素敵!
開館記念は見逃した映画特集。見たか見逃したか記憶がうろ覚えで、ずっと気になっていた幻の作品、牯嶺街少年殺人事件が掛かっているのを発見。正月3日までの上映で、行ける日は最終日の3日しかなく、夕方の6時開演で終わるのは10時と少し遅いのが気になったが、これは行くしかないと、意を決して吉祥寺へ
素晴らしく、打ちのめされた。映画に必要な要素がすべて込められており、映像を使った表現芸術の一つの完成形である。
4時間ずっと映画に惹きつけらたままで、どのシーンも見逃すまいと、食い入るように見ていたため、疲れたけど、満足。最後、坂道を転がり落ちるように絶望的な結末に突き進むところで、少しベティー。ブルーを思い出す。そういえば、どちらも1990年前後の同じ頃に撮られたんだよね。光と影のモザイク社会で、人生は不条理との葛藤であるという近代的不安を見事に描き切っている。打ちのめされました。
ちなみに、この映画観てました。いつ、どこでだったかはとんと思い出せないんだけど、最初と最後の合格者名の読み上げがラジオから流れてくるシーン、尋問室に冷房用の氷が置かれているシーンなど、デジャブを感じる。もしかしたら他の映画の似たようなシーンと勘違いしてるのだけかもしれないけど、きっと若い頃見てます。当時はこの映画の良さがまだわからず、途中寝落ちしてしまい、内容を覚えてなく、観た記憶がないのかもしれない。
家事と仕事に追われて、日記を書く心の余裕がない
その忙しさはまだまだ続いており、心の余裕はないままで、家事と仕事の忙しさについて愚痴を垂れるのは自分の無能ぶりを再確認するだけのようで歯がゆく、何も書く気になれない
そう言えば、この日記を書かなかった期間、映画館も美術館も行ってなく、庭仕事も山登りもやってない、本も仕事関連の資料しか読んでない
ということで、アマゾンでイギリスの人類学者ティム・インゴルドの訳本が新しく出ているのを見つけて、正月休み用に購入
毎日背表紙を見てニンマリしている、待ってろよ、インゴルド
さすがにこの本だけでは色気がないので、もう一冊喜怒哀楽に溢れた小説を探し中。青空文庫の谷崎かな
その忙しさはまだまだ続いており、心の余裕はないままで、家事と仕事の忙しさについて愚痴を垂れるのは自分の無能ぶりを再確認するだけのようで歯がゆく、何も書く気になれない
そう言えば、この日記を書かなかった期間、映画館も美術館も行ってなく、庭仕事も山登りもやってない、本も仕事関連の資料しか読んでない
ということで、アマゾンでイギリスの人類学者ティム・インゴルドの訳本が新しく出ているのを見つけて、正月休み用に購入
毎日背表紙を見てニンマリしている、待ってろよ、インゴルド
さすがにこの本だけでは色気がないので、もう一冊喜怒哀楽に溢れた小説を探し中。青空文庫の谷崎かな
上野の森でフェルメール
2018年11月28日 日常 コメント (2)まるでテレビを見てるような感じ
時間指定のチケット買って、指定時間に美術館の前で羊のように大人しく並んでたら、そんなに待たされず会場の中へ。最初から料金に含まれている音声ガイドもらって、やはりおとなしく並んで絵を鑑賞する。音声ガイドに従って、鑑賞の仕方まで教えてくれる。入場制限のためか会場はそんなに混んでなく、フェルメールの絵も、音声ガイドの石原さとみの声も、心地よい。
さらに作品数は多くなく、ネーデルランド絵画に飽きる前に出口に導いてくれる
う〜ん、何から何まで親切なのだ
アートって自由だと思っていたのに、お節介なテレビのように、何から何まで用意してくれていて、不思議な体験。私が今見たのはアートだったのか、それとも教養としての作品体験だったのかと
ちなみに、美術館がテレビ局や新聞社と共催して、目玉作品を用意して、メディアを通して大量の広告を打って、大量集客する美術展のことをブロックバスター展と呼ぶらしく、批判されるべき点もあるが、現代の日本ではおおむね肯定的に捉えられている
その対極にあり現代美術のメッカと言える品川の原美術館が再来年閉館するらしく悲しい、お客さんに媚びないあの方針好きだったのにな〜
そう言う私も毎回展覧会に行ってたわけではなく、 無くなるのは私たちの選択の結果でしょうがないかと。財団は建物の老朽化が一因なのでしょうがないと言ってるけどね
群馬の別館に集約して機能は残るらしいので、そちらであの媚びなさを発揮してもらうことを期待しましょう
時間指定のチケット買って、指定時間に美術館の前で羊のように大人しく並んでたら、そんなに待たされず会場の中へ。最初から料金に含まれている音声ガイドもらって、やはりおとなしく並んで絵を鑑賞する。音声ガイドに従って、鑑賞の仕方まで教えてくれる。入場制限のためか会場はそんなに混んでなく、フェルメールの絵も、音声ガイドの石原さとみの声も、心地よい。
さらに作品数は多くなく、ネーデルランド絵画に飽きる前に出口に導いてくれる
う〜ん、何から何まで親切なのだ
アートって自由だと思っていたのに、お節介なテレビのように、何から何まで用意してくれていて、不思議な体験。私が今見たのはアートだったのか、それとも教養としての作品体験だったのかと
ちなみに、美術館がテレビ局や新聞社と共催して、目玉作品を用意して、メディアを通して大量の広告を打って、大量集客する美術展のことをブロックバスター展と呼ぶらしく、批判されるべき点もあるが、現代の日本ではおおむね肯定的に捉えられている
その対極にあり現代美術のメッカと言える品川の原美術館が再来年閉館するらしく悲しい、お客さんに媚びないあの方針好きだったのにな〜
そう言う私も毎回展覧会に行ってたわけではなく、 無くなるのは私たちの選択の結果でしょうがないかと。財団は建物の老朽化が一因なのでしょうがないと言ってるけどね
群馬の別館に集約して機能は残るらしいので、そちらであの媚びなさを発揮してもらうことを期待しましょう